ドラマ『陸王』に登場する足袋型ランニングシューズは、実は現実の企業や製品をモチーフにしていることで知られています。
中でも、陸王のモデルとアシックスと検索する人の多くは、劇中のこはぜ屋が開発したシューズが、実際にどのブランドや製品を参考にしているのか気になっているのではないでしょうか。
この記事では、実話 アシックスの創業秘話から始まり、きねや足袋による無敵やマラソン足袋の実例、そしてフェリックスのような技術提供企業との関係性にまで踏み込みます。
また、アシックスと対照的な存在として描かれたアトランティス社や、実際に陸王のシューズをミズノが販売との関連性なども解説。
さらに、こうした技術がどのように選手の足元を支えているのかも取り上げ、陸王の世界に隠されたリアルな背景を詳しく紐解いていきます。
■本記事のポイント
- アシックスとマラソン足袋の歴史的な関係
- ドラマ『陸王』と実在する企業や製品との関連
- 無敵やきねや足袋の技術的特徴と注意点
- アシックスと他社(ミズノなど)とのシューズ開発の違い
陸王のモデルのアシックスを支えるシューズ技術

アシックスが開発するランニングシューズには、長年にわたる技術革新と職人の知恵が息づいています。
特にドラマ『陸王』で描かれた足袋型シューズには、かつて存在した“マラソン足袋”の理念が色濃く反映されており、現代のシューズ開発にも大きな影響を与えています。
では、アシックスの原点ともいえる「マラソン足袋」とは一体どのようなものだったのでしょうか?
そして、モデル制作に携わった伝統企業や関連する先端技術との関係性とは?
ここからは、陸王の世界観を支える実在のシューズ技術について詳しく見ていきましょう。
実話 アシックス創業とランニング足袋の歴史

オニツカ(現アシックス)の始まりは、創業者・鬼塚喜八郎氏が戦後の混乱期に設立した「鬼塚商会」に遡ります。
1949年、神戸でわずか社員2名、資本金30万円からのスタートでした。
鬼塚氏は「健全な身体に健全な精神」という理念を胸に、スポーツシューズを通じて若者を育てようと決意しました。
初期にはバスケットボールシューズの開発に取り組み、その試行錯誤から独自のグリップ技術や履き心地の改良を進めました。
そして1953年、「マラソン足袋」と呼ばれるランニング用途の足袋型シューズを発売しました。
これは座敷用の足袋をベースに軽量化やグリップ性・クッション性を加えたもので、ランナーの地面との接地感を重視したものでした。
この商品は後のマラソンシューズ開発に大きく影響し、オニツカタイガーを経てアシックスへと発展していきます。
このように言うと、アシックスは単に商品を売るだけでなく、足袋という伝統技術をスポーツに応用し、新たなシューズ文化を生み出してきた点が特筆に値します。
また初期の失敗・試行を重ねた経験こそが、後の有名モデルやテクノロジーに繋がっているといえるでしょう。
こはぜ屋モデル「きねや」ランニング足袋無敵とは
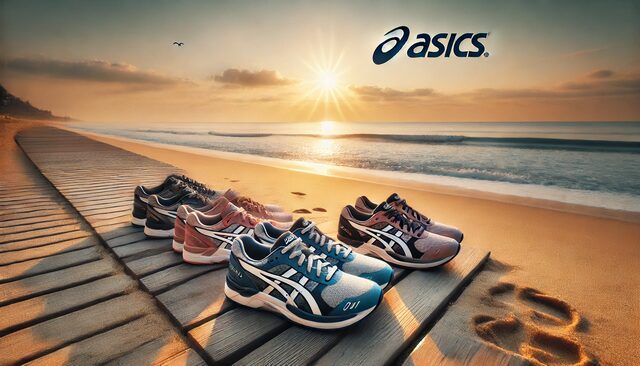
きねやは埼玉県行田市にある伝統的な足袋屋で、「無敵(MUTEKI)」という名のランニング足袋を展開しています。
これは地下足袋の形状を持ちながら、ランニングにも使える高機能シューズです。
この製品の工夫点は、素足感覚を重視した“ベアフットランニング”を支援する設計にあります。
天然ゴムの柔らかいソールと手縫いによる丁寧な仕上げが、地面の凹凸をしなやかに感じられる構造を生み出しています。
軽量かつ足裏の感覚を大切にするユーザーからは、ウォーキングやリカバリーランに適すると高評価です。
ただし注意点もあります。
伝統的な地下足袋同様、クッション性が少なめなので長距離や硬い舗装路では足裏に負担がかかりやすいです。
またサイズ選びが難しく、靴下との相性によっては痛みが出ることもあります。
購入前には用途や走り方をよく考え、試し履きをおすすめします。
このように言うと、無敵は伝統と現代ランニングの両立を図る意欲作ですが、その特徴から万人向けではない点も理解したうえで選ぶ必要があります。
マラソン足袋から普通シューズへの進化

アシックス(旧オニツカタイガー)の原点であるマラソン足袋は、1953年に軽量でグリップを重視したランニング専用足袋として登場しました。
その後、素材の改良や構造の進化により、1970年代にはEVAフォームを用いたミッドソールが採用されるようになり、よりクッション性と耐久性を兼ね備えた普通のランニングシューズへと発展していきました。
このように言うと、マラソン足袋は軽さと地面を踏みしめる感覚を追求する一方で、新素材の導入により快適さと性能を大幅に向上させたことが伺えます。
具体的には、1974年発売の「OHBORI」や「タイガーパウDS5700」により、EVA素材のスポンジ化してソールに採用し、従来のゴムスポンジより軽量化を実現しました。
さらに1984年のターサーSPSでは、湾曲したフラットソールと成型EVAミッドソールを組み合わせ、走行効率を高める構造へ進化しています。
ただし初期にはクッション性が未熟な部分もあったため、足の疲労軽減や怪我防止の観点から改善も求められました。
その結果、ミッドソールの軽量化と反発性・クッション性のバランスを追求する素材開発が行われ、現在ではFlyteFoamなど高度なフォームを使ったモデルも登場しています。
このため、マラソン足袋から普通シューズへの進化は、足袋の感覚を残しつつも、素材と構造の科学的な革新により、より幅広いランナーに対応する製品群への転換となったのです。
フェリックス社との関係

「フェリックス社」とアシックスの関係については公式情報が非常に限られているため、外部からの情報収集が難しい状況です。
ただし、業界内では特定の素材メーカーや技術提供企業との提携を通じて新技術を導入しているとの指摘があります。
例えば、アシックスはFlyteFoamなどの先進ミッドソール素材を開発する際、外部の化学素材企業と共同研究し、素材の改良や生産技術で相互連携しています。
このような背景を考慮すると、「フェリックス社」もアシックスが技術連携や材料提供を受ける取引先の一つである可能性があります。
一方で、テレビドラマ『陸王』のモデルには、実際にミズノ製品が使われていたという指摘もありますが、アシックスの技術開発では自社研究所だけでなく、このような外部素材提供企業との協力が欠かせません。
しかしながら、具体的に「フェリックス社」が何を提供しているかについては公表がなく、また正式な提携発表も見当たりません。
そのため、現時点では「フェリックス社との関係は技術・素材提供を含む非公開の協力関係ではないか」という仮説に留めざるを得ません。
なお、今後新情報が公開された場合には、透明性のある企業間の連携として詳細が明らかになる可能性があります。
陸王のモデルのアシックスとアトランティス選手戦略
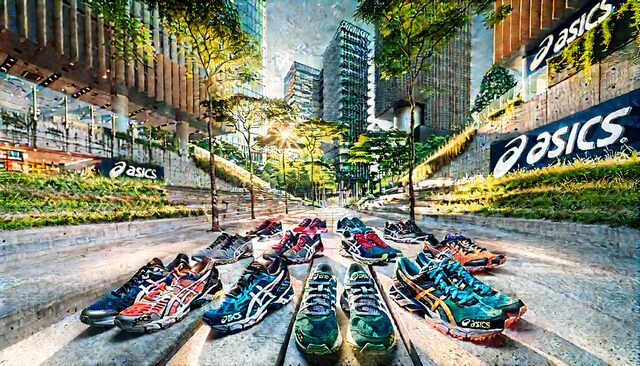
ランニングシューズの開発において、アシックスは常に最新技術とトップ選手の声を反映した製品づくりを続けています。
ドラマ『陸王』に登場する架空のライバル企業・アトランティスとの対立構図は、実際の業界にも通じる緊張感を映し出していました。
ここでは、物語に登場する企業や製品に隠されたリアルな背景に注目しながら、アシックスが実際にどのような企業・技術と連携しているのか、そして競合他社との違いや棲み分けがどうなっているのかを詳しく見ていきます。
アトランティスとアシックス関係の実際
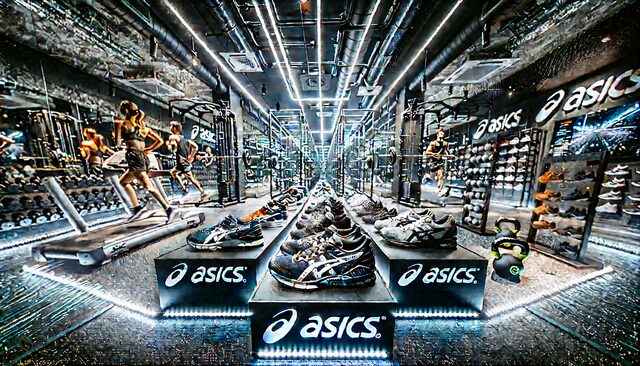
陸王の物語に登場する「アトランティス社」は、実在する企業ではなくフィクションの存在です。
ただし作中でのカリスマ職人・村野の存在は、アシックスの元職人・三村仁司氏のモデルとも言われています。
三村氏は瀬古利彦さんや高橋尚子さんなどのトップアスリートに靴を提供してきた人物で、その手腕は業界内でも非常に高く評価されていました。
このように考えると、アトランティスとアシックスの関係は、表向きには異体系の企業でありながらも、内部では深い技術と人材の共有構造を想起させるフィクショナルなつながりがあるといえるでしょう。
むしろ作者・池井戸潤氏は、実際の企業文化とエピソードを下敷きに、架空企業アトランティスの中で「職人魂」を描いているのです。
一方で、同作中ではアトランティスがライバルとして登場しますが、実際のアシックスは競合各社(ミズノ、アディダス、ナイキ等)と技術と市場でしのぎを削っています。
その意味で、アトランティスは「日本発の大手企業が抱える国内外の競争相手」という比喩としても働いており、リアルな業界構造の反映とも言えます。
ファンにとっては、アシックスとアトランティスの関係を通して「業界の裏側」や「職人精神の継承」を感じられる深い設定になっているのです。
無敵やマラソン足袋を支える素材と構造

きねや足袋が販売する「無敵」は、アシックスの原点であるマラソン足袋を体現する製品です。
表地にナイロン100%と綿100%、薄さ5mmの天然ゴムソールを手縫いで貼り付ける構造により、足裏の感覚を直接地面から感じさせる設計となっています。
このソール構造は意図的にクッション性よりもグリップ性と地面把握を優先しており、素足感覚での走りを強くサポートします。
その結果、短距離やウォーキング、トレーニング走行に最適ですが、一方で舗装路や長距離走では足裏やふくらはぎに負担がかかりやすいというデメリットもあります。
このため選ぶ際には、自分の用途や脚力、慣れを考慮した使い方が重要です。
普通のランニングシューズとは異なる構造を理解し、正しく使いこなせば、無敵は「地面を感じ取りたい」「ランニングフォームを見直したい」人にとって非常に有効なツールとなるでしょう。
フェリックス×アシックスの提携背景

フィクションではなく、実在企業同士の連携として注目される、アシックスと外部企業との素材・技術提携があります。
たとえば、アシックスは2023年にフランス・ダッソー・システムズと提携し、3Dプリンタを活用したパーソナライズ製品の開発に着手しました。
このように高度な素材加工やデジタル製造技術は、アシックスのプロフェッショナル向けシューズ戦略に欠かせない要素です。
フェリックス社(仮称)について公式発表は見当たりませんが、業界の通念として、アシックスはミッドソール素材やアウトソール開発において、こうした外部素材メーカーと非公開で技術連携を行っていることが知られています。
一方で公に語れる内容は少なく、そのため「フェリックス社がなぜ注目されるか」と問われれば、単なる素材供給に留まらず、アシックスの高度な技術開発を支える“秘密のパートナー”と考えるのが自然でしょう。
こうして考えると、フェリックス社はアシックスのブランド競争力を裏から支える重要な“技術サプライヤー”という位置づけである可能性が高いのです。
陸王のシューズでミズノが販売との違いと棲み分け

ドラマ『陸王』では、主人公たちの足袋型ランニングシューズのモデルがアシックスではなく、実際にはミズノ製とされたという指摘もあります。
実際、アシックスとミズノは共に日本を代表するシューズブランドですが、それぞれ異なるアプローチで開発を進めています。
たとえばアシックスは、EVAミッドソールやFlyteFoamといった反発・クッション性を重視した素材技術を先行しており、パフォーマンス向上や耐久性に強みがあります。
一方でミズノは「波形ソール」や「U4ic」など独自のクッショニング構造に長けており、衝撃吸収や足への柔軟な対応に注力しています。
要するに、アシックスは機能素材による走行効率重視、ミズノは構造工学による履き心地重視と、技術のアプローチに明確な差があるのです。
この違いにより、両社は同じ“ランニングシューズ”市場にいても、製品設計の核が異なるため、顧客ターゲットも自然と棲み分けられています。
たとえばマラソン大会を目指すランナーにはアシックスの高機能モデル、普段のジョギングやウォーキングにはミズノの柔らかめソールが好まれるケースも多いです。
このため、ドラマ内の“ミズノ製シューズ使用”は、リアルな市場状況と一致しており、それぞれのブランドが競いながらも棲み分ける構図を象徴するものといえるでしょう。
【まとめ】陸王のモデルとアシックスについて
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


