ランニングマシンの「速度10」は、有酸素運動としても脂肪燃焼の観点でも非常にバランスの取れたスピードです。
速度6の早歩きから始めた方や、速度9でのジョギングに慣れてきた方にとって、次のステップとして最適な目安となります。
この記事では、ランニングマシン 速度10を活用して効率よく痩せる使い方や、速度12や15といった上級者向けの走行との違い、そして男女別(女性・男性)の目標10km 時間に合わせたトレーニング方法についても解説します。
また、チョコザップなどのジム環境でも取り入れやすい設定や、HIITとしての応用、痩せる スピードを高めるコツについても触れていきます。
初めての方にもわかりやすく、おすすめの活用法を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
■本記事のポイント
- 速度10が有酸素運動に適したバランスのよいスピードであること
- 自分に合った速度や傾斜、運動時間の設定方法
- 速度10の使い方による脂肪燃焼や心拍数の管理方法
- 性別や目的別に応じた速度10の具体的な活用例
ランニングマシンの速度10で効果的な有酸素運動

ランニングマシンの「速度10」は、有酸素運動として非常にバランスの取れた速度です。
速すぎて続かないということもなく、遅すぎて効果が出にくいということもありません。
しかし、最大限の効果を引き出すには、速度だけに注目するのではなく、他の要素も合わせて理解することが大切です。
ここでは「速度6から9との違い」や「心拍数との関係」、さらに「痩せるためにどのように時間・傾斜・頻度を調整すべきか」などを詳しく解説していきます。
速度6から速度9の比較と使い分け
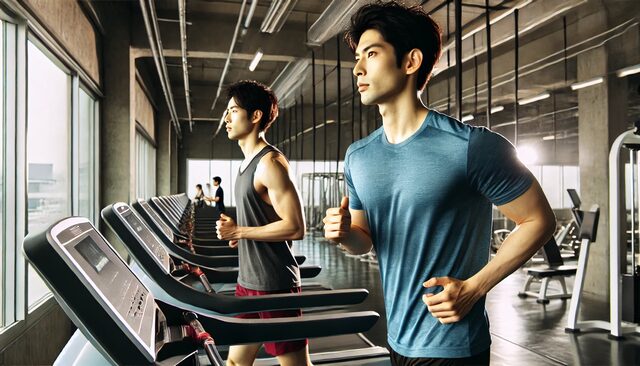
速度6(時速6km)と速度9(時速9km)は、ランニングマシンにおけるウォーキングとジョギングの境目と言えます。
時速6km前後では歩くのと走るの中間であり、自然とジョグに移行するラインとされています。
たとえば時速6.3kmでは軽い走りになりやすいという報告もあります。
一方、時速9kmは明らかにジョギングやランニングのペースです。
消費カロリーや心肺負荷が増えるため、体力や目的に応じて使い分けることが重要です。
理由としては、速度が上がるほどエネルギー消費量が指数関数的に増加するからです。
時速8kmを超えるとウォーキングとは桁違いの消費エネルギーとなり、ジョギング以上の強度になります 。
そのため、脂肪燃焼やトレーニング強度を意識するなら、目的別に速度を調整する必要があります。
具体的には、体力や運動目的に応じた速度の導入が有効です。
たとえば、「運動不足の解消」を目的とする初心者は速度6でウォーキング中心に20から30分行い、徐々に速度を上げていくのがよいでしょう。
一方、「心肺機能や筋力を向上させたい」場合は速度9を使って短時間ジョギングやインターバルトレーニングを取り入れると効率的です。
このように速度帯ごとに役割が異なるため、自分に合った設定を選ぶことが大切です。
有酸素運動としての痩せるスピードの目安

有酸素運動で脂肪燃焼を狙う場合、時速7から10kmが有効なスピード帯とされています。
これは「おしゃべりしながらでも続けられる」程度の中強度で、脂肪代謝が活性化しやすい強度です。
初心者であれば7から8km/hから始め、中級から上級者は速度を上げて30から40分程度継続するのが目安とされています。
理由としては、有酸素運動では開始から約20分後に体脂肪がエネルギー源になりやすくなる点が挙げられます。
その速度帯と継続時間を守ることで、糖質だけでなく脂質代謝が促進されて効率よく脂肪を燃やせるというわけです。
具体的には、初心者の場合は時速7.5kmで30分程度から始めるのがよく、体力向上とともに40から60分へ増やしていくスタイルが効果的です。
さらに、速度を一定に保つことに加え、ときには軽い傾斜(1から2%)をつけると、負荷を上げずに脂肪燃焼効果を向上させられます。
このように、速度と時間を適切に組み合わせることが成果につながります。
目安時間と最大心拍数の関係

有酸素運動の効果を高めるには、運動時間だけでなく心拍数も意識することが重要です。
最大心拍数(220から年齢が目安)のうち、60~80%の範囲内を目指すと、効率的に脂肪燃焼や心肺機能向上が期待できます。
たとえば30歳の方なら、最大心拍数は190拍/分で、その60~80%は約114~152拍/分です。
実際、時速7から10kmの中強度ではこの範囲に入りやすく、脂肪燃焼が促進されやすいとされています。
ただし同じ速度でも、傾斜をつけると心拍数はより上がりやすくなります。
たとえば傾斜1から2%の軽い坂でも、心拍数上昇が見られるため、運動の強度を微調整したい場合は傾斜を調整することが有効です。
具体的には、まずウォームアップとして平地(傾斜0%)で5分走り、その後1から2%傾斜で速度7から8km/hを20分続け、クールダウンで傾斜0に戻して5分ほど歩く流れが基本です。
また、運動中の心拍数をモニターし、135から145拍/分前後なら、脂肪燃焼に最適なゾーンと考えられます。
無理なく続けられる時間を守ることで、怪我のリスクを抑えながら効果を得やすくなります。
痩せる使い方:時間・傾斜・頻度

ランニングマシンで効率的に痩せるには「時間・傾斜・頻度」を戦略的に組み合わせることが大切です。
まず、痩せるために週に最低150分の中強度有酸素運動が推奨されています(アメリカ保健福祉省など)。
これを1回30分×週5回のスタイルで行うと無理なく継続しやすいでしょう。
さらに傾斜は、エネルギー消費を増やし、同じ時間でも消費カロリーを大幅に上げます。
たとえば傾斜10から15%でのウォーキングは、平地より20から44%も消費量が増えるケースもあります。
ただし急な傾斜は筋肉や関節への負担が大きくなるため、最初は3から5%から段階的に上げ、慣れてきたら最大12%程度を目指す方法が安全です。
頻度に関しては、週4から5回が標準的です。
とくに週に3回はインクライン設定で20から30分実施し、他の日に平地でインターバルや軽い有酸素運動を組み込むとバランスよく脂肪燃焼と体力向上が狙えます。
また、高頻度で同じトレーニングを繰り返すと怪我や停滞も生じやすいため、必ず回復日やストレッチ時間を確保することも忘れないでください。
速度12や15だとどうなの?

速度12(時速12km)や15(時速15km)は、ランニングマシンではかなりの高強度運動に分類されます。
これらの速度域では心拍数が最大心拍数の80から90%以上に達し、単なる有酸素運動ではなく、ほぼ無酸素運動やHIITに近い負荷になります。
実際、速度12以上だと多くの人が会話も難しくなるレベルで、短時間でもかなりの消費カロリーが期待できます。
しかし注意点として、膝・足首・腰への衝撃や怪我のリスクは格段に高まります。
したがって頻繁に導入するのは避け、週1回のインターバル形式で「30秒全力×1分回復」のようなHIITプランの一環として取り入れるのが安全かつ効果的です。
また速度12以上を継続する耐力がある程度ない場合、フォームが崩れやすくなり、逆に負担ばかりが増えてしまうケースもあります。
もしこの速度を目指すなら、まずは速度10で持久力をつけてから、少しずつ速度を上げて15秒速耐に移行する段階的アプローチがおすすめです。
ランニングマシンの速度10は男性・女性におすすめ?

ランニングマシンの「速度10」は、性別を問わず多くの人にとって取り入れやすい速度です。
しかし、体力や目的に応じて感じ方は大きく異なります。
たとえば、女性にとっては挑戦的なスピードであり、10km完走を目指す際の基準になりやすい一方、男性にとっては持久力を鍛えるための基礎的なペースとなる場合もあります。
また、HIITに活用したり、ジムサービスの中でどのような立ち位置なのかを知ることも重要です。
次に詳しく見ていきましょう。
女性向けの10km時間と効果的設定

一般的に、女性の10km完走タイムの目安は「約1時間3分~1時間6分」です。
たとえば30~34歳女性の平均は62分31秒程度、全世代を含めても約63分17秒が目安とされています。
この速度をランニングマシンで目指すには、ペースだけでなくトレーニング強度や頻度も重要です。
まずペース感をつかむために「時速10km」での走行を中心に30~40分続けてみてください。
この速度は女性にも取り組みやすい中強度で、会話がぎりぎりできる程度の負荷です。
また、週に1~2回は速度を落としてインターバルを取り入れる方法も有効です。
たとえば「時速8kmで3分間、時速10kmで2分間」というようにリズムを変えることで、心肺機能や脂肪燃焼効果をバランスよく高められます。
注意点として、最初から1時間を切る設定で無理してしまうと怪我のリスクが高まります。
このため、まずは週3~4回、速度8~10kmで20から30分を継続し、体力がついてきたら時間や速度を延ばしていくステップが長期的に効果的です。
男性向け速度設定と目安時間

男性の平均的な10km完走目安は「約55分30秒前後」であり、20~34歳男性では46~54分の間に位置するケースも多く見られます。
このタイムをマシン上で再現するには、速度10km以上への挑戦が現実的です。
まず時速10kmでの持久力をつけ、次のステップとして「速度10.5~11km」で心肺に負荷をかけます。
このレンジでは最大心拍数の70~80%に到達しやすく、効率的な脂肪燃焼とスタミナ強化につながります。
また、週1回は「速度12km程度で短時間インターバル(例:30秒全力+1分軽ジョグ)」を取り入れると、スピードアップに効果的です。
ただし、男性でも速度が上がるほど関節や筋肉への負担が大きくなるため、フォームチェックとストレッチ・回復日を忘れずに。
このように段階的な速度調整を行うことで、目安タイムを目指すだけでなく、安全なトレーニングが可能になります。
HIITにおける速度10の活用術

HIIT(高強度インターバルトレーニング)は速度10km/hを「中強度の繰り返し」に活かすのに最適です。
HIITは短時間で心肺能力や代謝向上に効果があると研究で示されています。
速度10を基準に、30秒全力と1分回復ペースにするなど、速度10を“回復期”に設定することで、無理なく高強度区間(例:速度12~14km/h)に移行しやすくなります。
こうすることでEPOC(運動後過剰酸素消費)効果が得られ、トレーニング後もカロリー消費が続きます。
また、速度10を安定して続けられる基礎持久力があることで、高速区間でもフォームの崩れを抑え、膝や腰への負担を軽減できます。
具体的には、ウォームアップ後に「30秒高速(12~14km/h)→速度10で1分回復」を10セット繰り返し、クールダウンに速度8~9km/hで5分ほど流す方法がおすすめです。
このパターンは初めてでも取り組みやすく、限界を超える前に回復できるので、安全に心肺機能アップと脂肪燃焼を両立できます。
チョコザップなどジムサービスでの速度10の位置づけ

チョコザップは低価格かつ24時間利用可能なジムで、トレッドミルにも柔軟な設定が可能です。
速度10km/hは中強度ゾーンにあたり、初心者から中級者まで多くの会員が使いやすい速度として重宝されています。
速度10で有酸素運動を続ければ、外ランニングのリズム感を保ちつつ、天候や道路条件に左右されず運動できます。
さらに、速度10を回復速度としてHIITに組み込む場合も、トレッドミルの傾斜や速度調整が簡単なので、サービス内で効率よく強度を高められるのもメリットです。
ただしジムでは会員が多数利用するため、トレッドミル使用時間は15分以内など制限があります。
そのため、速度10のトレーニングに加えて、自宅ランや屋外でも使える補完プランを立てると継続しやすくなります。
また、服装や靴底による摩耗で設備不具合が生じることもあるため、マシンの使い方や清掃ルールを守ることが大切です。
【まとめ】ランニングマシンで速度10について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


