ランニングを習慣にしていると、足裏や指にマメができるトラブルに悩まされることがあります。
特に、ランニングでマメの位置と検索している方は、親指や小指、土踏まずなど、どの部位にマメができやすいのか、そしてそれぞれに適した対策や予防方法を知りたいと感じているのではないでしょうか。
本記事では、ランニングでマメの位置ごとに起きる原因を解説し、テーピングや靴選びなどの具体的な対処法を紹介します。
また、足のマメを早く治す方法や、ランニングで水ぶくれができたときの正しい処置、豆ができたときの治し方は?といった疑問にもお答えします。
さらに、マメを放置するとどうなる?と不安を感じる方にも役立つ情報をまとめています。
安全かつ快適なランニングを続けるためのヒントを、ぜひ参考にしてください。
■本記事のポイント
- マメができやすい足裏や指の具体的な位置
- 部位別に異なるマメの原因と特徴
- 位置ごとの適切な予防・対策方法
- マメができたときの正しい処置と注意点
ランニングでマメの位置で多い足裏や指の発生箇所

ランニングを続けていると、気づかぬうちに足裏や指にマメができていた、という経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。
マメは単なる皮膚トラブルに思えるかもしれませんが、悪化すると痛みや走行フォームの乱れにつながることもあります。
特に発生しやすいのが、足裏の土踏まず付近や、親指・小指といった指先まわりの部位です。
ここでは、それぞれの部位にマメができやすい具体的な理由を掘り下げていきます。
足裏(土踏まず付近)にマメができる理由

足裏の土踏まず付近にマメができる主な原因は、靴やインソールとの摩擦や圧迫にあります。
まず、ランニング時には足のアーチが動くことで皮膚に「内部摩擦」が生じ、皮膚の上層と下層がずれて液体がたまることでマメができます。
それに加えて、土踏まずの形状に合わないインソールやアーチサポートが高すぎる場合、特定の部位が過度に圧迫されやすくなり、摩擦が強くなることでマメが生じやすくなります。
このような状態を防ぐには、自分の足のアーチに合ったシューズやインソールを選ぶことが重要です。
また、カーフストレッチや下腿の筋力トレーニングを行うことで、足のアーチの安定性を高め、皮膚にかかる横ずれ(シアー)力を減らせます。
さらに、摩擦を避けるためにアーチ部分にパッチやテーピングを貼ることで、マメの発生を抑える効果も期待できます。
親指と小指に水ぶくれがなりやすい
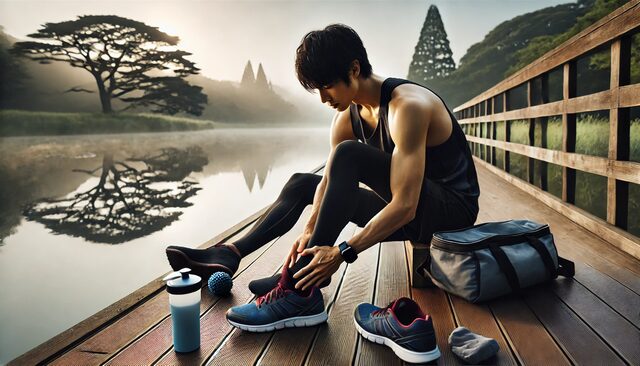
親指と小指はシューズ内で特に摩擦や圧迫を受けやすいため、マメができやすい部位です。
親指の場合、シューズが合わないと前方に圧迫され、皮膚が硬い部分に押され続けることで摩耗しがちです。
また、小指は外側に突出している構造のため、靴の幅が狭いと特に圧力が集中しやすい部位です。
さらに、小指には形状的に「曲がった第五指(adductovarus)」の人も多く、その場合突出した関節が靴に当たりやすく、摩擦によって水ぶくれが生じやすくなります。
こうした問題を抑えるためには、まず幅広のシューズ(ワイドモデル)やサイズアップしたモデルを選ぶことが効果的です。
さらに、摩擦軽減としてテーピングやジェルパッドを親指や小指に貼ることで、靴と皮膚の直接的なこすれを減らせます。
以上の対策を組み合わせると、特に親指や小指の水ぶくれを防ぐ確率が高まります。
シューズ内のズレ

足が走っている間に靴の中で前後や左右に動くと、特定の部位に摩擦が集中しマメができやすくなります。
ナイキやアシックスなどスポーツメーカーの専門家も、靴が大きすぎると足が遊びすぎ、小さすぎると皮膚と靴が擦れやすくなると指摘しています。
特に、走行中に土踏まずやかかと部分で足がズレると、内部摩擦(シアー)が発生しやすくなります。
このため、ランニング中のズレを防ぐには次の対策が有効です。
まず、夜間や運動後に試し履きし、足が靴の中で固定されているかを確認します。
さらに、かかと部分には「ヒールロック」などの特定の靴紐結び方(レーステクニック)を使うとズレが抑えられます。
その上で、カスタムインソールや履き慣らし期間を設けることで足と靴のフィット感が向上し、マメリスクを低減できます。
マメの位置に応じた圧迫ポイントの把握

身体の構造やランニングフォームによって、マメができやすい部位には傾向があります。
例えば、親指や小指、土踏まず、足の縁(エッジ部分)は圧力と摩擦が集中しやすいポイントです。
特に、ハイアーチ(高い足の土踏まず)や外反母趾などの足型の人は、着地や蹴り出しの際に特定の箇所が強く押される傾向があります。
そのため、まずはランニング後に足の皮膚の赤み・熱感・靴下の跡を観察しましょう。
これが圧迫ポイントの目安になります。
そして、そこに合わせてテーピング、摩擦軽減パッド、ジェルインソールを貼ると、複数の対策を組み合わせて効果的に摩擦を分散できます。
さらに、専用の滑り止めソックスや通気性のある素材で靴内の湿度を抑えると、湿った状態での摩擦を防ぎ、マメの発生リスクをさらに下げることが可能です。
ランニングでマメの位置をもとにした予防と対策
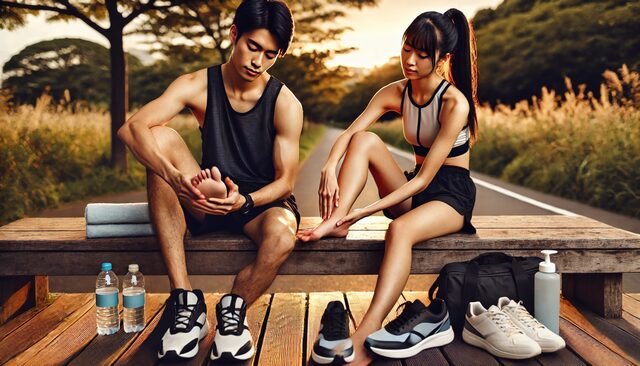
ランニング中にできるマメは、発生した位置によって適切な予防や対策方法が異なります。
特に親指や小指、土踏まず、足裏など部位ごとの特性に合わせたケアを行うことで、マメの再発を防ぎ、快適な走行を維持できます。
ここでは、それぞれのマメの位置に応じた具体的な対策や、万が一マメができてしまった場合の正しい処置方法について詳しく解説していきます。
痛みを我慢せず、早めに適切な対応をとることがパフォーマンス維持の鍵となります。
対策:テーピングや5本指ソックスで摩擦軽減

まずは摩擦が発生しやすいポイントにテーピングを活用しましょう。
伸びるタイプのキネシオテープや、より強力なリジッドテープ(ルコ・テープなど)は、ズレや摩擦の力を広い範囲に分散させ、保護を強化できます。
特に親指や小指、土踏まずなど“ホットスポット”に貼ると効果的です。
また、板テープの類は耐水性にも優れるため長時間のランにも向いています。
次に、5本指ソックスを履くことで指と指の間の摩擦を防ぎ、水ぶくれのリスクを大幅に軽減できます。
Injinjiなどのメーカーが展開するモデルには、足指を個別に包む構造により皮膚と皮膚が擦れず、通気性や吸湿性も優秀です。
さらに、ソックス自体に薄手のライナーを重ね履きする「二重ソックス」方式を採用すると、摩擦がソックス間で発生し皮膚への負荷が減るため、効果的です。
ただし、ソックスを重ねると靴が窮屈になる可能性もあるため、自分の足幅とのバランスを確認しましょう。
足裏ケア:ワセリンや専用クリームで摩擦予防

ワセリン(石油ゼリー)や専用のアンチチャフクリームは、皮膚と靴・ソックス間の接触面を滑らかにすることで摩擦を軽減します。
ただし、ランニングのように長時間・高温・多湿の状況では、約1時間程度で摩擦予防効果が低下するという観察もあります。
また、ワセリンは湿気を閉じ込めてしまうため、汗をかく足裏には不向きで、蒸れを助長し逆にマメを誘発する可能性もある点は注意が必要です。
その一方で、滑り止め効果を狙い短時間のトレーニングやレース前に限定して使用するのは有効です。
適度な量をマメができやすいポイントに塗布し、その後は速乾性のある専用アンチフリクションスティックやクリームに切り替えることで、快適さを維持しながら摩擦リスクを下げるバランスが取れます。
さらに、日常では乾燥しすぎないよう適度な保湿ケアも並行しましょう。
テーピング:親指や小指に局所保護を施す
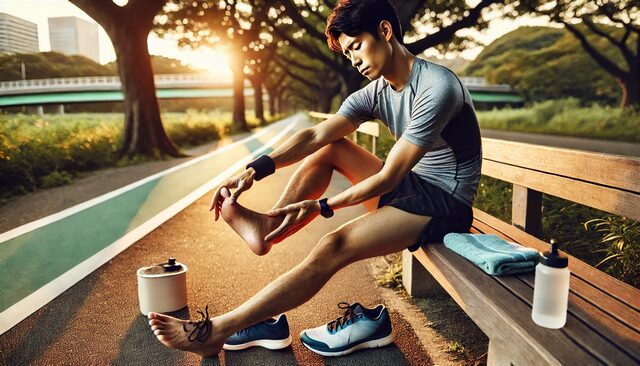
親指や小指はランニング中の摩擦が集中しやすいため、キネシオテープやブリスター用の粘着薄手テープを使って局所保護するのが効果的です。
たとえば、KTテープなどスポーツブランドの靴擦れ防止テープは、薄くて柔軟ながらも通気性に優れており、親指・小指の関節部分にぴったりフィットします。
これにより摩擦やこすれが広く分散され、水ぶくれリスクの軽減につながります。
実際、Redditのランニングコミュニティでも「ピンキー(小指)にキネシオテープのスリバーを貼る」といった具体的な使い方が共有されており、水ぶくれ対策として有効との声が多く見られます。
ただし、テーピングは長時間走ると粘着力が落ちることもあるため、特にレースや長距離走前には貼り直しや予備の用意をお勧めします。
土踏まずケア:クッション付きソックスで負担分散
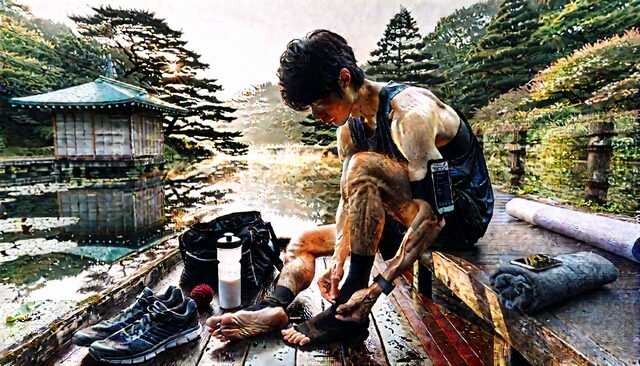
土踏まず部分にマメや痛みを感じる方には、クッション付きソックスやアーチサポート入りソックスが特に有効です。
例えば、FeeturesやSmartwoolなどは、中足部やかかとに厚めのパッドやアーチコンプレッションを設けており、靴との接触圧を緩和しながら湿気を逃がす素材構成が特徴です。
さらに、Wrightsocksの「ダブルレイヤー構造」は、内・外の2層のソックスが擦れ合うことで皮膚への直接摩擦を避ける仕様となっており、マメ予防に非常に効果的です。
ただし、重ね履き構造は靴内スペースを圧迫する可能性があるため、靴のサイズとのバランスを見ながら選ぶ必要があります。
これらのソックスは滑り止めや抗菌・防臭機能を備えたモデルも多く、長時間のランニングでも快適さを保ちやすい点も魅力です。
ただし、厚みが増すことで靴のフィット感が変化することがあるので、使用前に短時間の試走で確認すると安心です。
小指のマメ対処:靴幅調整と緩み防止

靴幅が狭すぎると、小指が靴内側に圧迫されて摩擦が集中し、水ぶくれや痛みの原因になります。
ピンキー(小指)マメの原因として、靴が「きつすぎ」「ゆるすぎ」「硬すぎ」のどれかに該当すると指摘されています。
靴ヒモやベルクロなどのフィッティング機能がある靴を選び、足が動きすぎるのを防ぐことが重要です。
また、夜間から翌朝にかけて靴を試し履きし、かかとがしっかり固定されているか、足幅が適切か確認しましょう。
加えて、ピンキー部分に粘着ジェルパッドやモールスキンを貼ることも効果的です。
これにより、靴との直接的な摩擦を防ぎつつクッション作用も得られます。
Redditでも「モールスキンを一枚貼ると問題解決した」という声があり、試してみる価値があります。
ただし、幅を足す調整をした結果、靴内でかかとが緩んだり靴紐の締めすぎで血流が滞る恐れもあるため、全体のフィット感を何度か調整しながら確かめることが大切です。
ランニングで水ぶくれの対処:刺さずに保護し絆創膏

水ぶくれができてしまった場合でも、基本は「破らない」で保護することが推奨されます。
封鎖型のヒドロコロイド絆創膏(例:CompeedやBand-Aid Hydro Seal)は、局所を保湿しながら外部からの細菌を防ぎ、自然治癒を促進します。
これにより治癒速度が50%速まり、また痛みも和らぐとされています。
ただし、大きな水ぶくれが既に破れている場合は、清潔な水や生理食塩水で優しく洗浄し、その後でアイランドタイプのパッドやガーゼを貼って保護します。
乾燥させることよりも、適度な湿潤環境を保つほうが感染リスクが低く、治りも早いとされるため、密閉タイプの絆創膏を選ぶと良いでしょう。
なお、絶対に刺したり水ぶくれを意図的に破ることは避けましょう。
専門家も「破ると感染リスクが高まる」と警告しており、むしろ保護絆創膏で覆う方が安全です。
ただし、強い痛みや圧迫感で走れない場合は、衛生的な環境で針を使い、底部に小さな穴を開けて液を抜くやり方もありますが、これはあくまで最終手段と考えましょう。
豆ができたときの治し方は?:消毒・保護で自然治癒促進
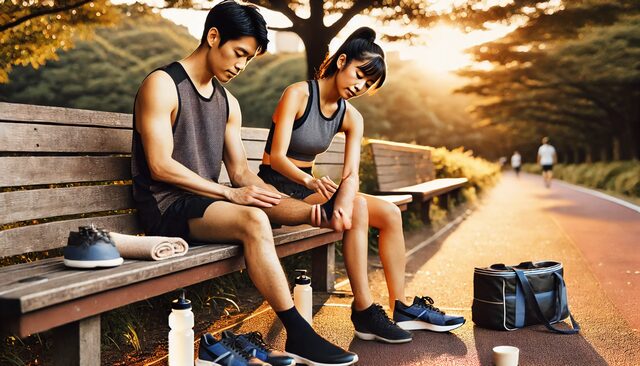
豆(マメ)ができたら、まずは清潔な状態を保つことが重要です。
破れていない状態であれば、あえて触らずに放置し、皮膚が自然に修復されるのを待ちましょう。
もし破れてしまった場合は、流水と抗菌石鹸でやさしく洗い、消毒液を使って清浄にします(例:消毒用アルコールやポビドンヨード)。
その後は、ヒドロコロイド絆創膏(CompeedやBand-Aid Hydro Sealなど)を使用すると、傷口を湿潤環境で保ちながら雑菌の侵入を防止でき、治癒を約50%速める効果が期待できます。
また、乾燥を避けるためには適度な保湿も必要です。
完治までには1~2週間ほどかかりますが、局部を絆創膏で覆ったままにしておけば痛みも和らぎ、日常生活や軽いランニングにも対応しやすくなります。
ただし、発熱・赤み・膿・異臭などの感染兆候が現れた場合は、すぐに医療機関を受診してください。
マメを放置するとどうなる?:感染リスクや痛み継続

マメをそのまま放置すると、まず痛みが長引いてランニングフォームが乱れることがあります。
無意識に負担の少ないフォームに変えてしまい、捻挫・腱炎など別のケガにつながる可能性もあるため注意が必要です。
さらに、マメが破れて開放創になると細菌の侵入リスクが高まり、化膿や蜂窩織炎(ほうかしきえん)といった重篤な皮膚感染症に進展することがあります。
最悪の場合、免疫力低下や糖尿病などがあると全身感染に至るケースも見られるため、マメに気づいた時点で適切な処置を行うことが不可欠です。
また、感染によって傷跡が残ることも珍しくなく、見た目の問題にもつながる可能性があります。
したがって、マメは軽視せず、早めに消毒や絆創膏で対処し、必要に応じて医療機関を利用するのが安心です。
【まとめ】ランニングでマメの位置について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


