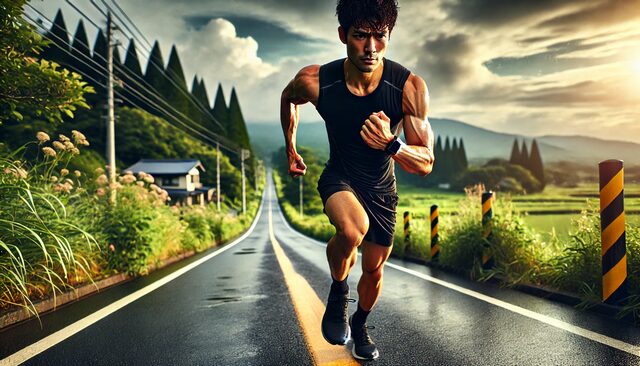ランニングを始めたばかりの方や、これからマラソンに挑戦したいと考えている方にとって、ランニングで1週間のメニューをどう組むべきかは非常に悩ましいテーマです。
ただ走るだけではなく、初心者でも無理なく続けられる「組み方」を知ることで、ケガを防ぎ、モチベーションを維持することができます。
筋力を補う「筋トレ」を取り入れたり、「スピード練習」で走力を伸ばしたりすることも効果的です。
また、「痩せる」ことを目的とする場合は、正しい「食事」との組み合わせも欠かせません。
最近では、メニュー作成アプリを活用し、自分に合った「トレーニングメニュー」を簡単に管理できる時代です。
マラソンの1週間練習メニューでサブ4や「マラソンの1週間練習メニューでサブ3を目指す方、あるいはマラソン初心者の練習メニュー やハーフマラソンの1週間練習メニューを探している方にも役立つ情報を、この記事では具体的にわかりやすく解説します。
■本記事のポイント
- ランニング1週間メニューの正しい組み方がわかる
- 筋トレやスピード練習の取り入れ方が理解できる
- 食事や栄養管理で痩せる方法が学べる
- メニュー作成 アプリを使った効率的な管理方法がわかる
ランニングの1週間メニューで初心者向け組み方

ランニングを始めたばかりの初心者にとって、「どのように1週間のメニューを組めばよいのか」は多くの人が悩むポイントです。
ただ走るだけでは継続が難しく、ケガやモチベーション低下につながることも少なくありません。
そこで、まずは無理のないペースからスタートし、徐々にスピードや負荷を高めていくことが重要です。
走りの効果を高めるためには、筋トレや食事、スピード練習をバランスよく取り入れることも欠かせません。
ここでは初心者でも安心して実践できる具体的なトレーニング方法をご紹介します。
初心者でも無理なく始めるトレーニングメニュー

初心者がランニングを始める際は、まず「無理なく継続すること」が最優先になります。
目標は週2から3回、1回30から40分程度のランニングで、会話ができるペースを基準にするとよいでしょう。
これは、月間50kmという段階的な目標が、継続力を育てるうえで有効とされているからです。
ウォームアップやストレッチを走る前後に5~10分ずつ取り入れることで、ケガを予防しながら正しいフォームを身につけられます。
このように進めれば、体への負担が少なく、精神的なハードルも下がるため、自然と習慣化につながります。
一方で、走行ペースだけにこだわると挫折しやすいため、「会話ができるくらいゆっくり走る」という感覚を大切にしてください。
例えば、最初はウォーキングとジョギングを交互にするインターバルスタイル(例:ジョギング5分+歩き5分の繰り返し)も有効で、継続しやすい工夫といえるでしょう。
ただし、初心者であっても、突然ペースや距離を伸ばすのは避けるべきです。
月間走行距離は前月比10%以内の増加に抑えると、ケガや疲労のリスクを軽減できます。
まずは小さな成功体験を積みながら、少しずつ距離や回数を増やしていくスタンスが最適です。
筋トレも組み合わせたバランス重視の体作り

ランニングの効果を最大化したい場合、筋トレを併用するのはとても効果的です。
有酸素運動と無酸素運動を組み合わせることで、脂肪燃焼力や基礎代謝が向上し、心肺機能にもよい影響が期待できるとされています。
具体的には、週2から3回の筋トレを取り入れ、大きな筋群(太もも、ふくらはぎ、体幹など)を中心に鍛えると効果的です。
このとき、目的によってトレーニングの順番を変えるとより効果的です。
脂肪燃焼を重視するなら「筋トレ→ランニング」、持久力アップを目指すなら「ランニング→筋トレ」の順番で行いましょう。
例えば、40分ほどの筋トレ後に30から60分ランニングを行えば、有酸素運動の効果が高まります。
ただし、トレーニング量を増やしすぎると疲労が蓄積してパフォーマンス低下やケガにつながるリスクがあります。
疲れている日は筋トレを軽めにするか、休息を優先するなど調整が必要です 。
具体的な筋トレ例として、ランニングで重要な下半身筋群をターゲットにする「スプリットスクワット」「スタンディングカーフレイズ」などが挙げられます。
前者は大腿四頭筋を、後者はふくらはぎを強化し、走りの安定性を上げるのに役立ちます。
自宅でもできる体幹トレーニング(プランクやヒップロール)も取り入れると、姿勢維持や疲れにくい走りにつながりやすくなります。
このようにランニングと筋トレを組み合わせれば、ただ走るだけのメニューに比べてバランスよく体を鍛えられるため、効率よく健康的な体づくりが可能になります。
もちろん、トレーニング後には十分なクールダウンと栄養補給を忘れずに行ってください。
スピード練習を取り入れるペース走の流れ
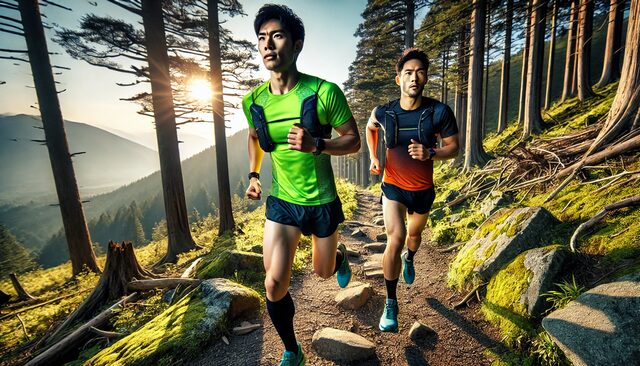
スピード練習をペース走に取り入れると、ランニングのパフォーマンスが確実に向上します。
まずウォームアップとして5~10分のジョギングを行い、心拍を上げてから本練習に移りましょう。
その後、週に1回程度「流し」やショートインターバルを取り入れます。
たとえば、決まった区間(100mや200m)を全力の約8割ペースで走り、その後ジョギングか歩きで休息を挟む方法です。
この方法は、速筋や心肺能力への刺激が得られ、全体的な走力アップに効果的です。
具体例としては以下のような流れが効果的です。
100mダッシュ×4~6本=ショートスプリントを週1~2回
慣れてきたら200mインターバル×5~10本などへ発展
週の練習に、ペース走(通常より10~20秒/km速め)を1回追加し、スピード持久力を鍛える
ただ、高強度の練習は週1回が目安です。
頻度を増やしすぎると疲労が蓄積し、故障のリスクが高まるため、走った後はクールダウンやストレッチをしっかり行い、身体のケアに努めてください。
痩せる効果アップの食事と栄養ポイント

痩せる目的でランニングを行う場合、食事はただ摂る・控えるではなく、栄養バランスを重視することが大切です。
特に重要なのは、PFC(タンパク質・脂質・糖質)のバランスを整えることで、健康的な減量と筋肉維持の両立が可能になります 。
食事の具体的なポイントは以下の通りです:
主食・主菜・副菜を揃えた定食スタイルを心がけ、PFCバランスを意識する
タンパク質は筋肉の回復に不可欠で、ランニング後は特に不足しないよう、体重1kgあたり1.3gを目安に
炭水化物はエネルギー源として重要だが、GI値やタイミングに配慮し、ランニング前3時間以内・後30~60分以内に摂取すると効果的
野菜・海藻・きのこや低脂質のたんぱく源(魚・豆製品・赤身肉など)を取り入れ、ビタミン・ミネラル・食物繊維も補う
ただし、注意点として「夜10時以降の食事」は避けたほうがよいとする研究もあり、減量中は食事のタイミングにも注意を払う必要があります 。
こうして食事内容とタイミングを見直せば、ランニング効果を最大限に活かした健康的な減量が可能になります。
ランニングの1週間メニューでサブ4/サブ3挑戦
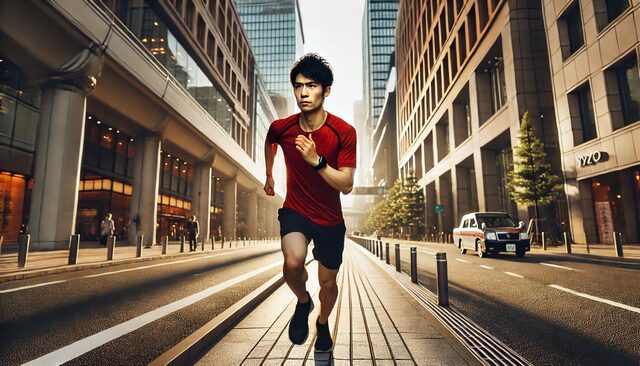
フルマラソンでサブ4やサブ3を目指すには、計画的な1週間メニューが欠かせません。
ただ走るだけでは目標達成は難しく、スピード・持久力・回復力をバランス良く鍛える必要があります。
特に限られた時間の中で効率的に練習を重ねることが重要です。
ここでは、サブ4・サブ3を狙うランナーに向けた、強度や負荷の考え方、そして具体的な1週間メニューをご紹介します。
それぞれの目標に合った適切な練習法を知り、あなたも自己ベスト更新を目指してみましょう。
マラソン練習メニューの1週間でサブ4向け強度設定
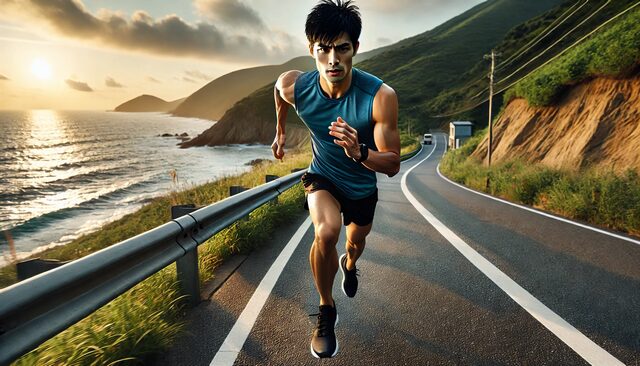
サブ4を目指すランナーにおいて、週の練習強度は「無理なく達成可能」でありながら目標ペースに慣れる内容を中心に組むことが効果的です。
具体的には、週4回の基礎ラン(イージーラン)に加え、1回のテンポランあるいはペース走、1回のインターバル走を含めます。
長距離は徐々に距離を伸ばし、たとえば10から14週目においては長距離ラン18~20マイル(約29~32km)を実施し、その後は軽めの調整週を設ける流れが推奨されています。
このように組めば、持久力・スピード・回復力のバランスがとれ、週の負荷と休息のリズムが安定します。
ただし、練習強度が高まるほど体の疲労も蓄積しやすいため、不調を感じた際は思い切って練習量を落としたり休息を優先する判断が必要です。
そうすることで怪我リスクを抑えつつ、理想的なペースでの走力向上を目指せます。
マラソン練習メニューの1週間でサブ3向け負荷との付き合い方

サブ3を狙うのであれば、週の走行距離は70マイル(約112km)以上が目安となる一方、20時間超の練習を要するケースもあるため、時間管理と疲労回復をどれだけ工夫できるかが鍵になります 。
練習の中心は長距離ラン、インターバル、VO2maxや閾値(テンポ)練習、さらにケガ防止や体幹強化のための補強トレーニングを週6回ほど取り入れるプランが一般的です。
このように負荷が高まる状況では、疲労サインを見逃さないことが重要です。
具体的には、睡眠の質・心拍の回復の遅さ・筋肉痛の引きずりなどを日々チェックし、身体の声に応じて練習を微調整します。
むしろこの柔軟な対応こそが、持続可能な高負荷トレーニングを可能にし、最終的なサブ3達成を現実的なものとします。
ハーフマラソンの練習メニューで1週間の具体例

週1回のポイント練習と3から4回のジョグを組み合わせることで、効率よく持久力とスピードを鍛えられます。
典型的な1週間構成は以下のとおりです。
月曜:完全休養 走力の回復を優先し、身体と心をリセットします。
火曜:ジョグ10から12km(Eペース)+ストレッチや体幹トレ 基礎持久力を維持しながら、身体の緩め補助を兼ねます。
水曜:ポイント練習①(インターバル) 400から1,000mインターバル×4から8本を、レースペースよりやや速めで実施し、スピードと乳酸耐性を強化します。
木曜:軽めジョグ8から10km ポイント練の疲労を抜くため、ゆったりしたペースでケア。
金曜:ポイント練習②(ペース走) 8~12kmペース走をMペース(レースペース+10から20秒/km)で行い、レースペースへの順応を高めます。
土曜:ジョグまたはクロストレーニング 疲労回復を意識しつつ、軽い運動で身体の循環を促します。
日曜:ロング走15から20km(ゆっくりペース) LSD(Long Slow Distance)を通じて持久力と心肺機能の底上げを図ります。
このプランは、ポイント練習を2回に抑えて疲労と効果のバランスを適切に取っています。
体調や疲労度に応じて、インターバルやペース走の日を前後にずらすと、さらに無理のない練習ができます。
メニュー作成アプリで効率的にプラン管理

ランニングの1週間メニューを自分で組むのは難しく感じますが、専用アプリを使えば効率的に管理できます。
自己ベストタイムや週の走行頻度を入力すると、あなたの実力に合ったプランを自動で生成する機能もあり、専門知識がなくても理論に基づいた練習が可能です。
また、最新のAI搭載アプリであれば、ウェアラブル端末(心拍・ペース・距離など)と連携し、リアルタイムにデータを分析しながら練習強度や内容を提案するものも登場しています。
Nike Run Club、ASICS Runkeeper、StravaなどのランニングアプリはGPSトラッキング、音声ガイド、トレーニングプラン機能、SNS共有といった多彩な機能を備えており、モチベーション維持にも一役買います。
ただし、アプリはあくまでサポートツールです。
自分の体調や日常リズムを考慮して、練習の強度や休養日の設定を柔軟に調整することが大切です。
適切な使い方をすれば、効率よく、継続しやすいメニュー管理ができ、確実な走力アップにつながっていきます。
【まとめ】ランニング1週間メニューについて
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。