ランニングシューズの寿命は、走る距離や頻度だけでなく、ナイキやアシックス、ミズノ、ニューバランス、ONなどブランド特有の素材や設計、そして普段履きの割合によっても変わります。
ソールやアウトソールの摩耗はどこを見ればよいのか、距離何キロで買い替えるのが妥当なのか、長い期間使うための手入れや保管のポイント、体重による違い、一般的に語られる1000kmという目安の根拠、もったいないと感じたときの判断、さらにランニングシューズを買い替えるサインは?まで、実用的な見分け方と考え方を整理して解説します。
■本記事のポイント
- 寿命の目安は「走行距離500~800km」「期間1~2年」に加え、アウトソールの摩耗やミッドソールのシワなど視覚的なサインで総合的に判断する
- 「厚底カーボンシューズ」はパフォーマンス重視のため寿命が短い傾向があり、ランナーの「体重」や「フォーム」によっても消耗スピードは大きく異なる
- 寿命切れのシューズを履き続けると、膝や足首への衝撃が増し「ランナー膝」などの怪我リスクが高まるため、違和感があれば早めの交換が必要
- シューズの寿命を延ばすには「2足以上のローテーション」や「正しい脱ぎ履き」が有効であり、買い替え時期はアプリで走行距離を管理するのが確実
ランニングシューズの寿命を見極める!距離・期間・見た目の判断基準
ランニングシューズの寿命を正確かつ多角的に判断するには、一つの基準だけに頼ってはいけません。
「数値(走行距離・期間)」による客観的なデータ管理と、「視覚・感覚」による現物チェックの両輪が必要です。
数値上はまだ走れるはずでも、保管状況が悪ければ素材は劣化しますし、逆に数値を超えても丁寧に扱えば長持ちすることもあります。
ここでは、買い替えのタイミングを絶対に見逃さないために知っておくべき具体的な基準について、詳細に解説します。
以下のポイントを総合的に照らし合わせることで、あなたのシューズが現在どのような状態にあるのかを正確に把握しましょう。
- 一般的な走行距離の目安と限界ライン
- 使用期間と経年劣化の関係
- アプリを活用した走行距離の管理方法
- アウトソールの摩耗状態の確認
- ミッドソールの劣化サイン
- アッパーやヒールカウンターの状態
- 身体に現れる不調や違和感
一般的な走行距離は500km~800km!距離1000kmは限界ライン
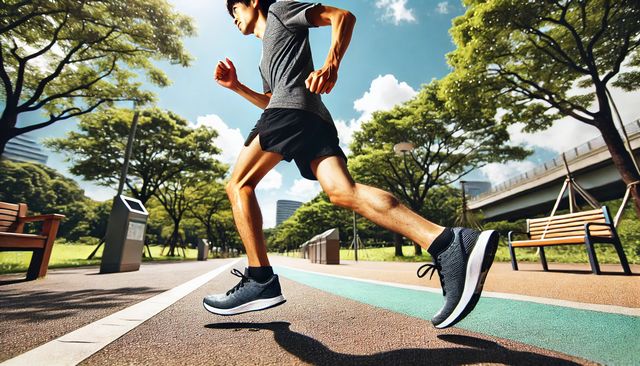
ランニングシューズの寿命を語る上で、最も基本的かつ信頼性の高い指標となるのが「総走行距離」です。
一般的に、ランニングシューズの機能が維持されるのは、走行距離500kmから800kmの間と言われています。
この距離の幅は、ランナーの体重や走法、路面の状況によって変動しますが、一つの目安として覚えておきましょう。
なぜこの距離が限界なのかというと、シューズの心臓部である「ミッドソール」の特性に関係があります。
着地時には体重の約3倍もの衝撃がかかりますが、ミッドソールの気泡構造が圧縮されることでその衝撃を吸収しています。
走行距離が伸びるにつれて、この気泡がつぶれたまま戻らなくなり、クッション性や反発力が著しく低下してしまうのです。
インターネット上には「1000kmまで問題なく履けた」という体験談も散見されますが、これを一般化するのは危険です。
1000kmという距離は、アウトソールのゴムが残っていたとしても、内部のクッション材は完全に機能を失っている可能性が高い「限界ライン」です。
車で例えるなら、タイヤの溝があってもサスペンションが壊れているような状態で、路面の衝撃を身体が直接受けることになります。
特に、まだ走るための筋力が十分に完成していない初心者ランナーの場合は注意が必要です。
衝撃を筋肉で受け止めることが難しいため、シューズの機能低下がそのまま関節へのダメージに直結してしまいます。
初心者のうちは、安全マージンを取って500kmから600kmあたりでの早めの交換を強く推奨します。
走っていなくても劣化する?使用期間と経年劣化の目安

「週末に数キロ走る程度だから、このシューズは数年は持つはずだ」と考えるのは、残念ながら誤りです。
ランニングシューズは工業製品であり、走行距離に関わらず、時間の経過とともに必ず劣化が進んでいきます。
これを「経年劣化」と呼びますが、主な原因はシューズに使用されている素材の化学変化です。
現在のランニングシューズの多くは、ミッドソールや接着剤にポリウレタンなどの樹脂素材を使用しています。
この素材は、空気中の水分と反応して徐々に分解されていく「加水分解」という現象を起こす性質を持っています。
| 用途/タイプ | おおよその目安距離 | 傾向 |
|---|---|---|
| レーシング寄り軽量モデル | 200から600km | 性能ピークが短く体感劣化が早い |
| デイリートレーナー | 400から1000km | 用途広くローテで伸びやすい |
| 厚底クッション系 | 400から800km | 反発よりも復元低下を体感しやすい |
| トレイルモデル | 300から800km | 路面条件で大きく変動 |
一度も履かずに箱に入れたまま保管していた新品の靴底が、数年後にボロボロと崩れ落ちることがあるのはこのためです。
具体的な期間の目安としては、製造から3年から4年、使用開始から1年から2年が機能維持の限界と考えましょう。
特に日本は高温多湿な気候であるため、海外に比べて加水分解が進行しやすい環境にあります。
クローゼットの奥にしまい込んでいたシューズを久しぶりに履く際は、必ずソールを手で曲げたり引っ張ったりして、剥がれやひび割れがないか確認してください。
見た目に大きな変化がなくても、素材が硬化していると本来のグリップ力やクッション性は発揮されません。
「あまり履いていないから」という理由だけで安全だと過信せず、購入からの経過期間も重要な寿命の指標として管理する必要があります。
アプリで管理!走行距離を記録して買い替え時期を通知する方法

「いつ購入したのか正確な日付を覚えていない」「合計で何キロ走ったのか計算できない」というランナーは意外と多いものです。
記憶に頼った管理は曖昧になりがちで、気づかないうちに寿命を大幅に過ぎてしまう原因となります。
この問題を解決する最適な手段が、ランニングウォッチやスマートフォンのアプリを活用した「ギアトラッキング機能」です。
Garmin Connect、Nike Run Club、Strava、TATTAといった主要なランニングアプリには、使用中のシューズを登録する機能があります。
この機能を活用すれば、日々のランニングデータを自動的にシューズごとの走行距離として積算し、管理することが可能です。
複数のシューズを練習用、レース用、雨の日用と使い分けている場合でも、それぞれの消耗度を一目で把握できるため非常に便利です。
さらに便利なのが、目標距離に達した際に通知を送ってくれるリマインダー機能です。
例えば「500kmに到達したら通知する」と設定しておけば、買い替えの検討時期をアプリが教えてくれます。
主観的な「まだいける」という感覚ではなく、客観的なデータに基づいて判断できるため、怪我のリスク管理として非常に有効です。
今までアプリを使っていなかった方も、この機会にシューズの登録を行ってみてください。
「このシューズとはこれだけの距離を一緒に走ってきたんだ」という愛着が湧くと同時に、適切な時期にお別れをする準備ができます。
ITスキルを少しだけ活用して賢くギア管理を行うことが、快適なランニングライフへの近道です。
アウトソールの摩耗と溝の消失

走行距離や期間のデータと合わせて必ず確認したいのが、現物の状態チェックです。
中でも最も分かりやすく、かつ重要な判断材料となるのが、地面と接する「アウトソール」の摩耗具合です。
新品の時はしっかりと刻まれていた溝が、どの程度残っているかを目視で確認しましょう。
通常、アウトソールには耐久性の高い硬質ゴムが貼られていますが、これが削れてなくなり、内側のミッドソール(白いスポンジ部分など)が露出していたら完全に寿命です。
スポンジ部分は摩擦に非常に弱いため、露出した状態で走ると一気に削れてバランスが崩れ、転倒や捻挫の原因になります。
また、ミッドソールまで削れていなくても、溝が浅くなり、雨の日や濡れたマンホールの上で滑りやすくなった場合も交換のサインです。
ここでもう一つ注目すべきなのが、左右のソールの減り方です。
通常は左右均等、もしくは利き足側がやや早く減る程度ですが、極端に左右差がある場合は注意が必要です。
片方だけ極端に外側が削れていたり、つま先部分だけが減っていたりする場合、ランニングフォームや骨盤のバランスが崩れている可能性があります。
このような状態で新しいシューズに履き替えても、またすぐに同じ箇所が削れて寿命を迎えてしまうでしょう。
シューズの買い替えは、自分の走りの癖を見直す絶好のチャンスでもあります。
極端な偏摩耗が見られた場合は、シューズ新調と合わせて、ランニング専門店でのフォームチェックや整体でのメンテナンスを検討することをおすすめします。
ミッドソールのシワ・硬化とクッション性の低下

アウトソールはまだ綺麗なのに、走ると足が痛くなる。
そんな時に疑うべきなのが「ミッドソール」の寿命です。
ミッドソールはシューズの機能の核心部分ですが、見た目の変化がアウトソールほど顕著ではないため、劣化が見過ごされがちです。
しかし、注意深く観察することで、確実に寿命のサインを見つけ出すことができます。
最も特徴的なサインは、ミッドソールの側面に現れる「細かい横ジワ」です。
新品のスポンジはハリがありますが、繰り返しの圧縮を受けることで徐々に復元しなくなり、潰れた状態のままシワとして残ります。
このシワが多数刻まれている場合、そのシューズのクッション性は既に限界を迎えていると判断して間違いありません。
また、「触感」によるチェックも有効です。
指でミッドソールを強く押してみて、弾力がなくカチカチに硬く感じるようであれば、素材が硬化しています。
新品時の「フワッとした反発感」や「足が包まれるような感覚」がなくなり、着地のたびに「ドン」という硬い衝撃を感じるようになったら危険信号です。
この状態のシューズで走り続けることは、コンクリートの上を薄い上履きで走っているのと同じような負荷を身体にかけます。
見た目が綺麗だからといって無理に使わず、素材の寿命を認めて潔く交換することが、足を守るためには不可欠です。
アッパーの破れ・型崩れとヒールカウンターの緩み
足の甲を包み込む「アッパー」や、かかとをホールドする部分の状態も、安全な走行には欠かせません。
アッパー素材には通気性の良いメッシュが使われることが多いですが、親指や小指が当たる部分は摩擦で破れやすい箇所です。
穴が開いていると、走行中に足がシューズ内で遊び、マメができたり爪が剥がれたりするトラブルの原因となります。
また、平らなテーブルの上にシューズを置いて、後ろから眺めてみてください。
もしシューズが左右どちらかに大きく傾いていたり、くの字に変形していたりする場合、それは「型崩れ」を起こしています。
型崩れしたシューズは、履くだけで足首を捻った状態にしてしまうため、非常に危険です。
さらに確認してほしいのが、かかと部分に入っている芯材「ヒールカウンター」の強度です。
かかとを指でつまんでみて、簡単に潰れてしまうほど柔らかくなっていませんか。
ヒールカウンターが緩むと、着地した瞬間に踵がぐらつき、アキレス腱や足首周辺に過度な負担がかかります。
特に、靴紐を解かずに脱ぎ履きしていると、このヒールカウンターが早期に破損します。
ソールがまだ残っていても、アッパーやヒールカウンターが足を支えられなくなったら、そのシューズはランニング用としての役割を終えています。
ホールド感の喪失は、パフォーマンス低下だけでなく、転倒事故にもつながる重要なチェックポイントです。
走った後の足の痛みや違和感

ここまではシューズ自体に現れるサインを見てきましたが、最も正直なのは「あなたの身体の感覚」です。
「最近、以前と同じ練習メニューなのに練習後に膝や足首が痛む」「翌日まで疲れが残りやすくなった」と感じることはありませんか。
その原因を、自身の筋力不足や体調不良、あるいは加齢のせいにして片付けてしまうのは早計かもしれません。
身体に現れる原因不明の不調は、シューズのクッション性喪失による衝撃増加が原因であるケースが多々あります。
劣化したシューズは衝撃を吸収しきれず、そのエネルギーが破壊的な負荷となって関節や筋肉にダイレクトに伝わります。
身体が「もうこの靴では衝撃を受け止めきれない」と悲鳴を上げている状態、それが痛みや違和感の正体です。
特に、シンスプリント(すねの内側の痛み)や足底筋膜炎(足の裏の痛み)といったランニング障害は、シューズの劣化と密接に関連しています。
もし不調を感じているなら、一度スポーツショップで新品のシューズを試着し、そのクッション性の違いを確認してみてください。
新品の弾力に驚くようであれば、今履いているシューズは確実に寿命を迎えています。
※健康・安全に関する注意:
痛みや違和感が長期間続く場合や、歩行時にも痛みがある場合は、シューズを交換するだけでなく、必ず整形外科やスポーツ専門医を受診してください。
自己判断での放置は症状を悪化させ、疲労骨折などの重篤な怪我につながる可能性があります。
【タイプ別】ランニングシューズの寿命は厚底・メーカー・ランナーの特徴で変わる

「走行距離500km」というのはあくまで平均的な目安に過ぎず、全てのシューズに一律に当てはまるわけではありません。
実際には、シューズの構造(厚底か薄底か)、各メーカーの設計思想、そして使用するランナーの特性によって、耐久性は大きく異なります。
平均値を鵜呑みにせず、自分が使っているモデルや自分の特徴を考慮した上で、個別に寿命を判断する必要があります。
ここでは、より専門的な視点から寿命の違いを深掘りし、あなたの状況に合わせた判断基準を提供します。
以下の3つの視点から、それぞれの特性と寿命の関係性を詳しく見ていきましょう。
- カーボンプレートや厚底シューズの特性
- メーカーごとの耐久性の傾向
- ランナーの体重やフォームによる影響
カーボンプレートや厚底シューズ(HOKA・ナイキ等)の寿命は短い?

近年、マラソン界を席巻している「厚底カーボンシューズ」ですが、これらは一般的なシューズとは寿命の考え方が異なります。
特にナイキの「ヴェイパーフライ」シリーズなどに代表されるトップレーシングモデルは、注意が必要です。
これらのシューズは、「速く走ること」を最優先に設計されており、極限まで軽量化し、高いエネルギーリターンを得るために特殊な素材を使用しています。
その代償として、耐久性は意図的に低く設定されている傾向があります。
採用されている高反発フォーム(ZoomXなど)は非常に繊細で、最高のパフォーマンスを発揮できる期間は「300kmから400km程度」と言われることも珍しくありません。
高価なシューズだから長く持つはずだというのは誤解であり、むしろ高価なレーシングカーのように、パーツの消耗が早いのです。
練習用とレース用を分けずに、このようなレーシングシューズで毎日のジョギングを行っていれば、あっという間に寿命を迎えてしまいます。
コストパフォーマンスを考えるならば、ポイント練習やレース本番だけ厚底カーボンを履き、普段のジョグには耐久性の高いモデルを選ぶべきです。
一方で、HOKA(ホカ)などの厚底シューズ全てが短命なわけではありません。
「クリフトン」や「ボンダイ」といったトレーニング向けのモデルは、分厚いミッドソールが高い耐久性を持ち、800km以上履けることもあります。
重要なのは、その厚底シューズが「決戦用(レーシング)」なのか「練習用(デイリートレーナー)」なのかを正しく理解し、用途に合った使い方をすることです。
ミズノ・ニューバランス・アディダスなどメーカーによる耐久性の違い

各スポーツメーカーやシリーズによっても、耐久性に対する設計思想には明確な違いがあります。
もちろんモデルごとの差はありますが、一般的な傾向を知っておくことはシューズ選びの参考になります。
例えば、ミズノやアシックスといった日本メーカーは、部活動でのハードな使用環境を想定して開発されてきた歴史があります。
そのため、アウトソールに採用されるゴム(X10やAHARなど)は非常に耐摩耗性が高く、長持ちしやすいという定評があります。
「とにかく丈夫で長持ちする靴が欲しい」というニーズに対しては、日本メーカーのデイリートレーナーモデルが最適解になることが多いでしょう。
アディダスは、「ブーストフォーム」や「ライトストライク」といった独自のミッドソール素材が高い耐久性を誇ります。
しかし、アウトソールに採用されている「コンチネンタルラバー」は、タイヤメーカーとの共同開発による強力なグリップ力が特徴です。
グリップ力が高いということは、それだけ路面との摩擦が大きいことを意味するため、走り方によっては摩耗が早まる場合もあります。
ニューバランスやナイキは、世界的なシェアを持ち、モデル展開が非常に幅広いのが特徴です。
クッション性を重視したモデルから、素足感覚を重視した軽量モデルまで多岐にわたります。
特に「軽量性」を売りにしているモデルは、アウトソールのゴムを極限まで薄くしたり、部分的に省略したりしているため、ソールが削れやすい傾向があります。
ブランド名だけで判断せず、そのシューズがどのようなコンセプトで作られているかを確認することが大切です。
意外と知らない!体重やランニングフォームが寿命に与える影響
シューズの寿命を決定づけるのは、靴自体の性能だけではありません。
「誰がどう履くか」という、ランナー側の要素も寿命に大きな影響を与えます。
「500km」という基準は、あくまで平均的な体重と標準的なフォームのランナーを想定したものです。
物理的な法則として、体重が重いランナーほど、一歩ごとの着地衝撃は大きくなります。
衝撃が大きければ大きいほど、ミッドソールの圧縮率は高くなり、復元力の低下(へたり)も早く進行します。
体重が重めの方や、筋肉量が多いガッチリした体型の方は、平均よりも寿命が短くなることを見越して、早めの交換サイクルを意識する必要があります。
また、ランニングフォームの癖も消耗のスピードを左右します。
「ドタバタ」と大きな音を立てて走る着地は、衝撃をうまく逃せていない証拠であり、シューズへのダメージも甚大です。
さらに、地面を強く蹴りすぎたり、ブレーキをかけるような着地をしたりすると、摩擦熱と物理的な研磨によってアウトソールが急速に削れます。
極端なヒールストライク(かかと着地)の人はかかとの外側が、フォアフット(つま先着地)の人は前足部の中央が集中的に摩耗します。
特定の部分だけに負荷が集中する走り方をしている場合、シューズ全体としてはまだ綺麗でも、部分的な寿命を迎えてしまうことがあります。
自分の体重や走り方の特性に合わせて、「自分にとっての寿命基準」を見つける視点を持つことが、怪我のないランニングには不可欠です。
ランニングシューズの寿命を過ぎても履き続けるリスクと「その後」の活用法
「高かったシューズだから捨てるのはもったいない」「まだ履ける気がする」という心理は、誰にでも働くものです。
しかし、その「もったいない」という判断が、結果的に高い医療費や治療期間を招くことになってしまっては本末転倒です。
ここでは、寿命切れのシューズを履き続けることの具体的なリスクと、役目を終えたシューズの活用法について解説します。
- 怪我のリスクと身体への負担
- パフォーマンス低下への影響
- ウォーキングや普段履きへの転用
- 適切な処分のタイミングと方法
膝や足首への負担増による怪我のリスク

ランニングシューズの最大の役割は衝撃吸収ですが、寿命を迎えたシューズはその機能を失っています。
クッション性が低下した状態で走り続けるということは、着地のたびにアスファルトの硬さをダイレクトに身体で受け止めることを意味します。
この衝撃は、足首、膝、股関節、さらには腰へと伝わり、蓄積されていきます。
これが引き金となって発生するのが、ランニング障害と呼ばれる慢性的な怪我です。
代表的なものに、膝の外側が痛む「腸脛靭帯炎(ランナー膝)」、すねの内側が痛む「シンスプリント」、足の裏やかかとが痛む「足底筋膜炎」などがあります。
これらの怪我は一度発症すると完治までに時間がかかり、数週間から数ヶ月間、走ることを禁止される場合もあります。
走る楽しみを奪われるだけでなく、通院のための時間や治療費もかかります。
新しいシューズ代の数万円を惜しんだ結果、それ以上の損失を被ることになるリスクを、決して軽視してはいけません。
自分の身体を守るための「必要経費」として割り切り、予防的にシューズを交換することが、長く健康に走り続けるための賢い選択です。
反発力低下によるパフォーマンスとタイムへの悪影響

寿命を迎えたシューズの弊害は、怪我のリスクだけではありません。
ランニングのパフォーマンス、特にタイムや走行効率にも悪影響を及ぼします。
現代のランニングシューズは、着地エネルギーを次の一歩への推進力に変える「反発性」を重視して設計されています。
しかし、ミッドソールがへたって反発力がなくなると、地面を蹴る力が前方への推進力に変換されにくくなります。
その分、自分の筋力を使って前に進まなければならず、同じペースを維持するために余計なエネルギーを消費することになります。
結果として、レース後半での失速や、練習での過度な疲労蓄積を招くのです。
また、すり減ったソールによってシューズのバランスが悪くなると、着地が不安定になります。
身体は無意識にバランスを取ろうとして変な部位に力を入れたり、フォームを歪めたりしてしまいます。
一度ついた悪いフォームの癖を矯正するのは難しく、長期的な成長の妨げにもなりかねません。
「良い道具」を使うことは、実力以上の力を出すためではなく、自分の実力を100%発揮し、正しい動きを身につけるために必要なのです。
ランニング用をウォーキングや普段履きに転用するメリット・デメリット
「ランニングには使えないけれど、捨てるには忍びない」というシューズには、第二の人生を用意してあげましょう。
結論から言えば、ランニング用としての寿命を迎えたシューズでも、ウォーキングや普段履きへの転用は十分に可能です。
歩くという動作は、走る動作に比べて着地衝撃がはるかに小さいため、多少クッション性が低下していても、膝や腰への悪影響は限定的だからです。
通気性が良く軽量なランニングシューズは、長時間歩く旅行や、立ち仕事、近所への散歩用としては依然として優秀です。
また、庭仕事や洗車、DIYなどの「汚れても良い作業靴」としてストックしておくのも良いでしょう。
こうして最後まで使い切る用途を決めておけば、ランニング用から引退させる際の心理的な抵抗感も減らすことができます。
ただし、転用する際にも注意点はあります。
アウトソールが極端に斜めに削れている場合は、普段履きにするのも避けるべきです。
傾いた靴で長時間歩くことは、歩行姿勢を歪め、O脚やX脚を助長したり、骨盤のズレを引き起こしたりする原因になります。
また、派手な蛍光色などのデザインが多いランニングシューズは、日常のファッションと合わせにくい場合もあるため、使うシーンを選ぶ工夫も必要です。
感謝を込めて手放すタイミングと処分の方法

普段履きとして第二の人生を全うした後、いよいよ本当の最期が訪れます。
ウォーキング用としてもソールが滑るようになったり、アッパーが破れて見た目がみすぼらしくなったりした時が、手放すべきタイミングです。
多くの自治体では「燃えるゴミ」や「燃えないゴミ」として処分することになりますが、地域のルールを必ず確認してください。
ただゴミとして捨てることに抵抗がある場合は、リサイクルプログラムを活用するのもおすすめです。
一部の大手スポーツショップや、ナイキなどの直営店では、ブランドを問わず不要になったシューズを回収するボックスを設置しています。
回収されたシューズは粉砕され、テニスコートや陸上トラックの路面材、公園の遊具の素材などとして再利用されます。
あなたの足を守り、長い距離を共に走り抜いた相棒が、形を変えてまた誰かのスポーツを支えることになる。
そう考えれば、感謝の気持ちを込めて手放すことができるはずです。
サステナブルな方法で適切に処分することも、自然の中を走るランナーとしての嗜みと言えるでしょう。
1日でも長く履くために!ランニングシューズの寿命を延ばす「3つの習慣」

どんなに優れたシューズにも寿命はありますが、日頃の扱い方一つでその寿命を延ばすことは可能です。
お気に入りのシューズを大切にし、コストパフォーマンス良くランニングを続けるために、今日からできる具体的なメンテナンス習慣を紹介します。
面倒な手入れは続かないという方でも、以下の3点だけは意識してみてください。
日々のちょっとした心がけが、シューズの持ちを劇的に変えます。
- 2足以上のローテーション
- 正しい脱ぎ履きの徹底
- 適切な保管とメンテナンス
2足以上を使い分けるローテーション効果

ランニングシューズの寿命を延ばすために最も効果的、かつプロも実践している方法が「ローテーション」です。
つまり、「毎日同じ靴を履かない」ということです。
これには、ミッドソールの素材であるスポンジの特性が深く関係しています。
ランニングによって体重で圧縮されたスポンジが、元の形状や弾力に完全に戻るまでには、一般的に24時間から48時間程度の休息が必要とされています。
毎日同じシューズを履き続けると、スポンジが回復しきらないうちに次の衝撃を受けることになり、「へたり」が加速度的に進行します。
人間と同じで、シューズにも休息が必要なのです。
最低でも2足のシューズを用意し、交互に履くようにするだけで、1足を履き潰して買い換えるサイクルを繰り返すよりも、トータルの使用期間を延ばすことができます。
また、性格の違うシューズ(例:クッション重視のモデルと、軽量性重視のモデル)を履き分けることは、足への刺激を変え、特定の筋肉への負担集中を防ぐ効果もあります。
怪我予防と寿命延長の一石二鳥の効果があるローテーションを、ぜひ取り入れてみてください。

シューズの寿命を自ら縮めてしまう最大の要因の一つが、脱ぎ履きの際の「横着」です。
面倒だからといって、紐を結んだまま無理やり足をねじ込んだり、脱ぐときにかかとを反対の足で踏んで脱いだりしていませんか。
これらの行為は、シューズの構造を一瞬で破壊します。
特にかかと部分に入っている「ヒールカップ」は、足を安定させるための重要なパーツですが、踏み潰すと折れ曲がり、二度と元には戻りません。
ヒールカップが壊れたシューズは、フィット感が著しく損なわれ、靴擦れや捻挫の原因になります。
どれだけソールが残っていても、かかとが潰れたらその靴は寿命です。
毎回必ず紐を解き、履き口を広げてから足を入れ、かかとをトントンと合わせてから紐を結ぶ。
脱ぐときも必ず紐を解いてから手を使って脱ぐ。
この当たり前の習慣を徹底するだけで、アッパーの寿命は劇的に延びます。
「靴べら」を使って履くことも、かかと内側の生地の擦り切れを防ぐために非常に有効です。
加水分解を防ぐ保管方法とメンテナンス

走り終わった後のシューズの扱いも重要です。
使用直後のシューズ内部は、汗で湿気が充満しています。
そのまま下駄箱に放り込むと、雑菌が繁殖して悪臭の原因になるだけでなく、湿気によって素材の加水分解が進行します。
帰宅後はインソールを取り出して湿気を逃し、直射日光の当たらない風通しの良い場所で陰干ししましょう。
また、泥汚れが付着したまま放置すると、生地の繊維に入り込んで劣化を招きます。
泥がついた場合は、ブラシで軽く落としておく習慣をつけましょう。
汚れがひどい場合は水洗いをしたいところですが、頻繁な水洗いは接着剤の劣化を早めるリスクもあります。
基本的には中性洗剤を薄めた液で拭き取るか、専用のシューズクリーナーを使用し、水洗いは数ヶ月に1回程度に留めるのが無難です。
絶対にやってはいけない保管場所は、夏場の車の中や直射日光の当たるベランダです。
高温環境下では、ソールの接着剤が溶けたり、樹脂パーツが変形したりと、一発でシューズをダメにする可能性があります。
涼しく通気性の良い場所で休ませてあげることが、シューズへの一番の労りです。
【まとめ】ランニングシューズの寿命について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


