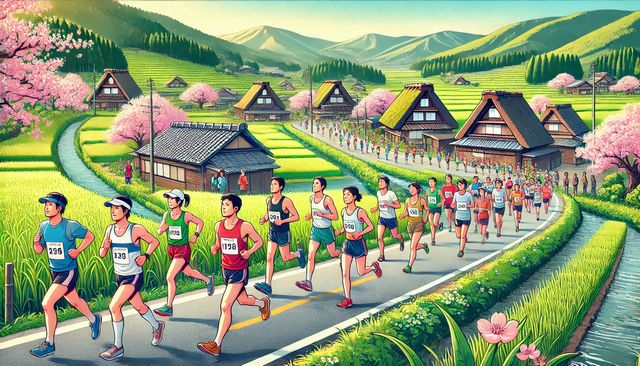ウルトラマラソンのシューズを選ぶ際は、距離特有の負荷や時間の長さを見越した視点が欠かせません。
大会で見かけるホカオネオネやアシックス、ナイキ、アディダス、ON、ブルックス、ニューバランス、ミズノ、アルトラなど各ブランドの特徴は多彩で、初心者が迷いやすいポイントも多いです。
サブ10サブ9を視野に入れる場合は、クッション性や安定性に加え、推進力を補うカーボンの活用も検討材料になります。
市場や大会運営の公開情報をもとにした調査では、厚底化と軽量化の両立が進んでいるとされます。
メンズの体格傾向を踏まえた設計や、サイズの微調整がしやすいラスト設計も重要です。
本記事では、失敗しない選び方とおすすめの考え方を体系的に整理し、ブランド別の特徴やサイズ選びのコツまで網羅します。
■本記事のポイント
- 長時間の走行でも膝や腰への負担を最小限に抑えるため、「クッション性」と疲労時のフォームを支える「安定性」が不可欠であることを解説しています
- レース後半の激しい「むくみ」を想定し、普段より0.5から1.0cm大きめを選ぶべき理由と、マメや爪割れを防ぐ正しいフィット感の確認方法を提示しています
- HOKAやアシックスなどの最新おすすめシューズを紹介するとともに、完走狙いのランナーには「カーボンプレート」が逆効果になり得るリスクについても触れています
- ドロップバッグを活用した「シューズ履き替え戦略」や、高機能ソックスの活用、ヒールロックなどの結び方といった、現場で役立つトラブル回避術を伝授しています
ウルトラマラソン専用シューズの選び方と必要な3つの機能
フルマラソン経験者であっても、100kmウルトラマラソンは全く異なる競技だと捉える必要があります。
競技時間の長さと身体への負荷が桁違いであるため、シューズに求められる機能も変化するからです。
ここでは、完走するために不可欠な要素を以下の5つの観点から解説します。
- 10時間以上動き続ける身体への衝撃と負担の大きさ
- 後半の失速を防ぐために専用シューズが必要なワケ
- 100km完走を支える衝撃吸収とクッション性の高さ
- 疲労時のフォーム崩れをカバーする安定性とガイド機能
- 長時間の着用でもストレスを感じない軽さと通気性
10時間以上動き続ける身体への衝撃と負担の大きさ

ウルトラマラソンでは、一般的に10時間から14時間ほど体を動かし続けることになります。
この長時間運動がもたらす身体への負荷は計り知れません。
ランニングにおける着地衝撃は体重の約3倍と言われています。
体重60kgのランナーであれば、一歩ごとに約180kgの負荷がかかります。
フルマラソンでの歩数が約3万歩から4万歩であるのに対し、ウルトラマラソンでは8万歩から10万歩に達します。
単純計算でも、関節や筋肉が受ける衝撃の総量はフルマラソンの2倍以上となります。
これほど膨大な衝撃を受け続けると、足裏の皮膚、足首、膝、股関節、そして腰椎に深刻なダメージが蓄積されます。
筋肉の損傷だけでなく、着地衝撃による内臓への揺れも無視できません。
長時間の振動は消化器官の不調を招き、補給食を受け付けなくなる原因にもなります。
したがって、ウルトラマラソンでは「いかに速く走るか」よりも「いかに衝撃を殺して体を守るか」が最優先事項となります。
身体を守るプロテクターとしての機能がシューズには求められます。
後半の失速を防ぐために専用シューズが必要なワケ

レース後半、特に60kmから70km地点を過ぎると、多くのランナーは脚の筋肉が限界を迎えます。
太ももの前側(大腿四頭筋)やふくらはぎが悲鳴を上げ、自分の意思とは関係なく足が止まる現象が起きます。
この状態では、きれいなランニングフォームを維持困難になります。
腰が落ち、膝が曲がった状態での着地が増え、ベタ足気味になるランナーが多く見られます。
フォームが崩れると、衝撃を筋肉で吸収できなくなり、骨や関節へダイレクトに負担がかかります。
フルマラソン用の薄底シューズや軽量性重視のシューズでは、この局面で足を保護しきれません。
ウルトラマラソン専用、あるいは適したシューズは、フォームが崩れた状態でも着地をサポートする設計がなされています。
疲労困憊の状態でも足を前に運んでくれる機能が必要です。
自分の筋力が終わった後、残りの距離を「シューズの機能」で走らせてもらうという感覚を持つことが、完走への近道となります。
100km完走を支える衝撃吸収とクッション性の高さ

前述した膨大な衝撃から身を守るために最も重要な機能が、ミッドソールの「クッション性」です。
ミッドソールとは、足裏と靴底のラバーの間にあるスポンジ状のパーツを指します。
ウルトラマラソンでは、この層が分厚く設計された「厚底シューズ」が圧倒的に有利です。
近年のランニングシューズ市場では、マキシマムクッションと呼ばれる極厚ソールが主流になりつつあります。
厚みのあるミッドソールは、着地時の衝撃を物理的に変形することで吸収し、足へのダメージを分散させます。
コンクリートの硬さを感じさせない柔らかさは、後半の足持ちを劇的に良くします。
ただし、単に柔らかいだけでは沈み込みすぎてしまい、蹴り出しに余計な力が必要になります。
そこで重要になるのが「反発性」とのバランスです。
着地のエネルギーを次の一歩につなげる適度な反発力があることで、少ない筋力で巡航速度を維持可能になります。
最新の素材は、マシュマロのような柔らかさとバネのような反発性を両立させています。
疲労時のフォーム崩れをカバーする安定性とガイド機能
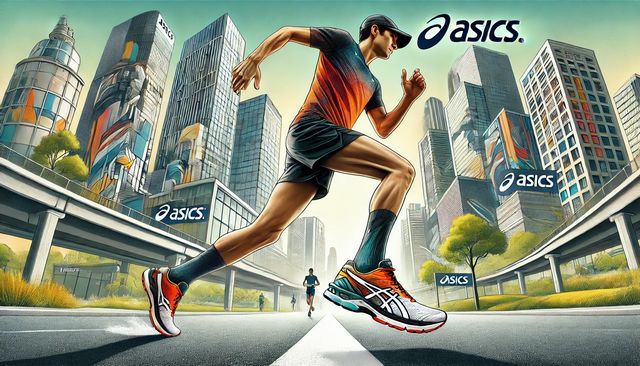
長時間の走行で足のアーチ(土踏まず)が落ちてくると、着地した瞬間に足首が過度に内側に倒れ込む「オーバープロネーション」が発生しやすくなります。
これが膝の内側の痛みやシンスプリント(すねの痛み)の大きな原因となります。
これを防ぐのがシューズの「安定性(スタビリティ)」です。
ウルトラマラソン向けのシューズには、靴底の接地面積を広くしてグラつきを抑える工夫や、かかと周りを硬い素材で補強して倒れ込みを防ぐ機能が搭載されています。
また、「ガイド機能」や「ロッカー構造」と呼ばれる、つま先が反り上がった形状も重要です。
ロッカー構造は、ゆりかごのようにコロンと転がる動きをシューズが作り出してくれます。
足首やふくらはぎの筋肉を使わずに重心移動だけで前に進めるため、省エネ走行が可能になります。
疲れて足が上がらなくなった終盤でも、シューズが転がることで一歩が出る。
このサポート機能が完走率を大きく左右します。
長時間の着用でもストレスを感じない軽さと通気性

クッションや安定性を高めると、どうしてもシューズの重量は増してしまいます。
しかし、10万回足を上げるウルトラマラソンにおいて、「重さ」は敵です。
片足数グラムの差であっても、トータルでは何トンもの重量を持ち上げる計算になります。
そのため、保護機能と軽量性のバランスを見極める必要があります。
一般的に、ウルトラマラソンで完走(サブ10から完走ギリギリ)を目指す場合、片足250gから300g(27.0cm基準)程度が目安とされています。
最近のシューズは素材の進化により、見た目のボリュームに対して驚くほど軽量化が進んでいます。
実際に手に取り、重さを確認することをおすすめします。
また、「通気性」も軽視できない要素です。
長時間靴を履き続けると、靴内部の温度と湿度が上昇します。
皮膚がふやけると摩擦に弱くなり、巨大な水ぶくれ(マメ)ができやすくなります。
アッパー素材(足を包む布部分)にエンジニアードメッシュなど通気性の高い素材が使われているかどうかも、トラブル回避の重要なチェックポイントです。
ウルトラマラソン用シューズでサイズ選びの正解とカーボンシューズについて
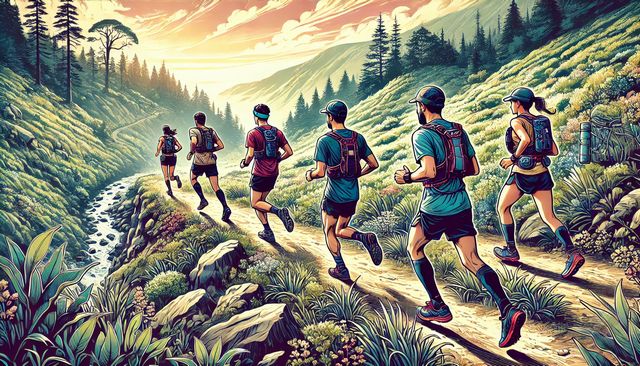
ウルトラマラソン特有の悩みとして、多くのランナーが直面するのが「サイズ感」と「カーボンプレート搭載シューズの是非」です。
フルマラソンと同じ感覚で選ぶと失敗する可能性が高い領域です。
ここでは、以下の4つのポイントについて、具体的な判断基準を提示します。
- ウルトラマラソンではシューズ大きめを選ぶのが常識か
- 実走でのトラブルを防ぐサイズ感とフィット感の確認方法
- 初心者や完走狙いのランナーにカーボンをおすすめしない理由
- サブ10や記録更新を狙う上級者にとってのカーボンのメリット
ウルトラマラソンではシューズ大きめを選ぶのが常識か

結論から申し上げますと、ウルトラマラソンにおいては「普段のランニングシューズより0.5cmから1.0cm大きめ」を選ぶのが定石とされています。
その最大の理由は、長時間の走行によって発生する「足のむくみ」と「アーチの低下」です。
50km、60kmと走り続けると、重力と衝撃によって足の裏のアーチ(土踏まず)がつぶれて下がってきます。
アーチが下がると、足の長さ(足長)と幅(足囲)が物理的に広がります。
さらに、血液やリンパ液の循環が悪くなることで足全体がむくみ、体積が増加します。
もしジャストサイズのシューズを履いていると、レース後半に靴内部が窮屈になり、つま先が靴の先端に当たり続けます。
その結果、爪下血腫(爪が黒くなり死ぬ現象)や激痛を伴う圧迫骨折のような状態に陥ります。
これを防ぐために、最初からむくみ分を想定した「捨て寸(つま先の余裕)」を確保する必要があるのです。
実走でのトラブルを防ぐサイズ感とフィット感の確認方法
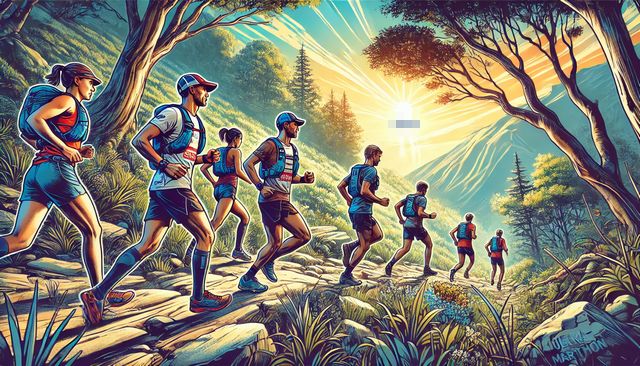
大きめのサイズを選ぶといっても、単にぶかぶかの靴を履けば良いわけではありません。
靴の中で足が前後左右に滑ってしまうと、摩擦熱で火傷のような水ぶくれができたり、爪を痛めたりする原因になります。
「指先は自由だが、足の甲とかかとは固定されている」状態が理想です。
試着時の確認ポイントとして、まず踵をトントンと地面に合わせてヒールカップに収めます。
その状態で靴紐をしっかり締めた際、つま先に親指の幅一本分(約1.0cmから1.5cm)程度の余裕があるか確認してください。
指をグーパーと動かせる空間が必要です。
一方で、足の甲(中足部)はしっかりとアッパー素材が密着し、ホールドされている必要があります。
ここが緩いと下り坂で足が前に突っ込んでしまいます。
また、くるぶし周りや踵が浮かないかも歩いて確認しましょう。
夕方以降、足がむくんだ状態で試着に行くと、より本番に近い感覚で選定可能です。
以下はサイズ調整の目安を整理した表です。
| 状況 | 推奨の対処 |
|---|---|
| 指先が当たる | ハーフサイズ上げる、シューレースで甲を緩める |
| 横に遊ぶ | ワイズを狭めるか、アッパー保持力の高いモデル |
| 甲の圧迫 | アイレットの通し方を工夫、タン位置を再調整 |
| 踵が抜ける | ヒールロック結び、踵カップの形状が合うモデル |
初心者や完走狙いのランナーにカーボンをおすすめしない理由
近年、マラソン界を席巻している「カーボンプレート搭載シューズ」。
反発力でタイムを短縮できる魔法の靴として人気ですが、ウルトラマラソンの完走狙い(キロ6分から7分ペース)のランナーには、手放しではおすすめできません。
カーボンプレートは硬い板です。
その反発力を活かすには、ある程度のスピードと、プレートをしならせるだけの踏み込む筋力が必要です。
ゆっくりとしたペースで走る場合、プレートの硬さが仇となり、着地のたびに足裏やふくらはぎへ突き上げ感を食らうことになります。
また、カーボンシューズは推進力を生むために不安定な構造になっているものが多くあります。
疲労してフォームが崩れた際、この不安定さを制御しきれず、足首や膝への負担が増大するリスクがあります。
完走が目標であれば、反発性よりも安定性とクッション性を優先し、ノンカーボンまたは柔軟性のあるナイロンプレート等のモデルを選ぶ方が賢明です。
サブ10や記録更新を狙う上級者にとってのカーボンのメリット
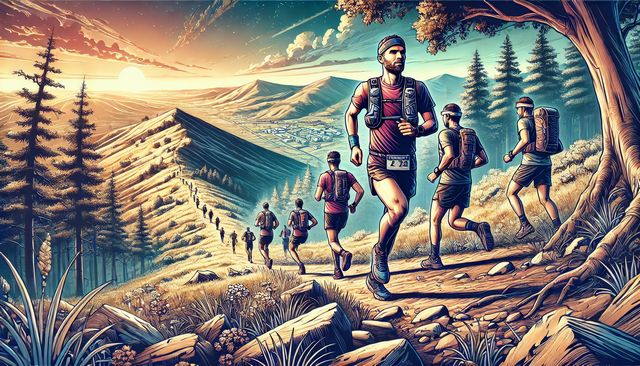
一方で、100kmを10時間以内(サブ10)で走ることを目指すレベルのランナーにとっては、カーボンシューズは強力な武器になります。
サブ10達成には平均キロ6分を切るペース維持が必要です。
この速度域であれば、カーボンの恩恵を受けやすくなります。
後半、筋力が低下して足が前に出なくなった時でも、カーボンの反発力が強制的にストライド(歩幅)を伸ばしてくれます。
少ないエネルギーで巡航速度を維持できるため、心肺機能への負担軽減も期待できます。
ただし、フルマラソン用の上級者向け薄底カーボンシューズ(ナイキのヴェイパーフライなど)は、100kmの衝撃吸収には不向きな場合があります。
各メーカーから発売されている、クッション厚がありつつカーボンを搭載した「トレーニングモデル」や「ロング走向けモデル」の中から選ぶと、保護と推進力のバランスが良くおすすめです。
【2026年最新】ウルトラマラソンおすすめシューズランキング
ここからは、2025年1月時点での市場トレンドと機能を踏まえ、ウルトラマラソンに最適なシューズを具体的なカテゴリー別に紹介します。
ご自身の目標や足の形に合わせて、最適な一足を見つける手がかりにしてください。
以下の3つの視点で解説します。
- 徹底調査!初心者におすすめの人気ウルトラマラソンシューズ
- アシックスやニューバランスなどブランド別の特徴と選び方
- メンズランナー必見の幅広ワイドモデルとフィット感
徹底調査!初心者におすすめの人気ウルトラマラソンシューズ

初めてのウルトラマラソン完走を目指す方には、何よりも「足を守る機能」に特化したシューズがおすすめです。
このカテゴリーで不動の人気を誇るのが「HOKA(ホカ)」のシューズです。
特に「Bondi(ボンダイ)」シリーズは、ブランド史上最も厚いクッションを持ち、雲の上を歩くような感覚が得られます。
着地衝撃を極限まで減らしたいランナーの定番です。
同じくHOKAの「Clifton(クリフトン)」シリーズも人気です。
ボンダイより軽量でバランスが良く、どんなペースにも対応できる万能モデルです。
HOKAの特徴である「メタロッカー構造」により、転がるように足が出る感覚は、疲労した後半に大きな助けとなります。
また、On(オン)の「Cloudmonster(クラウドモンスター)」も注目です。
特徴的な空洞のあるソール形状が、着地時に潰れて衝撃を吸収し、爆発的な反発を生み出します。
楽しく弾むような感覚で走れるため、長時間の苦痛を和らげてくれるでしょう。
これらの「マックスクッション」カテゴリーから選ぶのが、完走への王道です。
アシックスやニューバランスなどブランド別の特徴と選び方
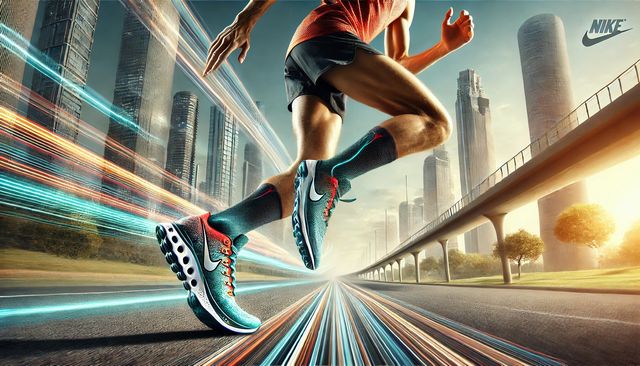
日本人の足型を知り尽くした国内ブランドや、機能性に定評のある大手ブランドも強力なラインナップを揃えています。
アシックスの「GEL-NIMBUS(ゲルニンバス)」シリーズは、カシミアのような上質な履き心地を追求したモデルです。
かかとのホールド感とクッションの柔らかさは秀逸で、多くのウルトラランナーに愛用されています。
また、アシックスの「NOVA BLAST(ノヴァブラスト)」シリーズは、トランポリンのような反発性が特徴です。
楽しくリズムよく走りたいランナーに適しています。
一方、ニューバランスの「Fresh Foam More(フレッシュフォーム モア)」は、HOKAに対抗する極厚ソールモデルです。
接地面積が広く安定感が抜群で、横ブレを防ぎたい方におすすめです。
海外ブランドは幅が狭い傾向がありますが、ニューバランスはウィズ(足囲)サイズ展開が豊富で、甲高幅広のランナーでもジャストフィットを見つけやすいのが強みです。
自分の足の形に合うブランドを見極めることが重要です。
以下の表では主要ブランドを比較し、それぞれがどのようなランナーに適しているかを整理しました。
| ブランド | 主要特長 | クッション傾向 | 安定性傾向 | 足型の傾向 | 向くランナー像 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホカオネオネ | 厚底とロッカー | 非常に柔らかめ | 中から高 | やや広めあり | 長時間の衝撃緩和を優先 |
| アシックス | ガイド機構と一体感 | 中からやや柔らかめ | 高 | 標準からワイド | 安定感とフォーム維持 |
| ナイキ | 反発重視のフォーム | 中から柔らかめ | 中 | 標準 | 巡航速度重視 |
| アディダス | 耐久とグリップ | 中 | 中から高 | 標準 | 練習量が多い |
| ON | 着地安定と推進の両立 | 中 | 中から高 | やや細めから標準 | ロードの長時間走 |
| ブルックス | 安定設計と耐久 | 中 | 高 | 標準からワイド | 安心感重視 |
| ニューバランス | 豊富なラスト | 中 | 中 | 細めからワイド | フィット重視 |
| ミズノ | ブレを抑える支持 | 中 | 高 | 標準 | フォーム安定 |
| アルトラ | 広い前足部とゼロドロップ | 中 | 中 | 広め | 自然な足指の動き |
メンズランナー必見の幅広ワイドモデルとフィット感

日本人男性ランナーには、足の幅が広い「幅広(ワイド)」や甲が高い「甲高」の特徴を持つ方が多くいます。
海外製の標準幅(Dワイズなど)では、小指が圧迫されたり、甲が締め付けられたりして、長時間の走行に耐えられないことがあります。
そこで注目すべきは「ワイドモデル(2E、3E、4E、SWなど)」の展開有無です。
アシックスやミズノ、ニューバランスなどの主要ブランドは、同じモデルで「スタンダード」と「ワイド(またはスーパーワイド)」を用意していることが多くあります。
HOKAもワイドサイズを展開するモデルが増えています。
無理して幅の狭い靴をサイズアップして履くと、つま先が余りすぎてつまずきの原因になります。
足長は合わせつつ、横幅にゆとりのあるワイドモデルを選ぶことで、適切なホールド感と快適性を両立できます。
特にウルトラマラソンでは後半のむくみで横幅が広がるため、普段は標準幅の人でも、ウルトラ用にワイドモデルを選ぶケースも少なくありません。
ウルトラマラソン用シューズで完走を確実にする履き替え戦略とトラブル対策

シューズ選びと同じくらい重要なのが、本番での運用方法と周辺アイテムの活用です。
100kmという長丁場では、状況に合わせて環境を変えることがリスク分散になります。
ここでは、一歩進んだ完走テクニックとして以下の6つを解説します。
- ドロップバッグを活用して足の感覚をリセットする効果
- 前半は反発系で攻めて後半は保護系で守る具体的戦術
- 月間走行距離200km以上をこなすためのコスト管理術
- 本番用シューズの性能を最大限発揮させる慣らし期間
- シューズの性能を引き出す高機能ソックスの重要性
- 足首をしっかり固定するヒールロックなど結び方の工夫
ドロップバッグを活用して足の感覚をリセットする効果
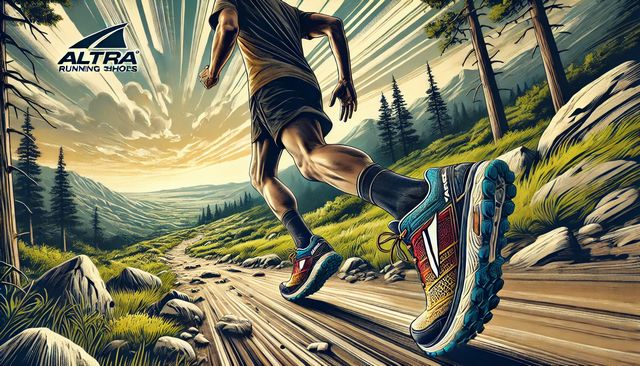
多くのウルトラマラソン大会では、コースの中間地点(50km付近など)に「ドロップバッグ」と呼ばれる荷物を預けることができます。
ここに予備のシューズを入れておき、レース中に履き替える戦略は非常に有効です。
同じシューズを10時間以上履き続けると、靴内部の湿度が飽和状態になり、足裏の特定の場所に圧力がかかり続けます。
ここでシューズを履き替えると、湿った環境がリセットされ、圧迫されるポイントも微妙に変わります。
これだけで「生き返った」ように足が軽くなる感覚を得られます。
また、精神的なリフレッシュ効果も絶大です。
「あそこまで行けば靴を替えられる」という短期目標ができることで、中盤の苦しい時間帯を乗り切るモチベーションになります。
予備シューズは、履き慣れた古いシューズでも構いません。
トラブル回避の保険として準備しておくことを強く推奨します。
前半は反発系で攻めて後半は保護系で守る具体的戦術

シューズの履き替えを行う場合、機能の異なる2足を使い分ける戦術があります。
前半の50kmは、まだ脚に元気があり、ある程度のペースで貯金を作りたい時間帯です。
ここでは、適度な反発性と軽量性のあるシューズ(例:アシックス ノヴァブラストやHOKA クリフトンなど)を選びます。
そして疲労がピークに達する後半50km用に、クッション性と保護機能を最優先したマックスクッションシューズ(例:HOKA ボンダイやニューバランス Fresh Foam Moreなど)を投入します。
さらに、後半用のシューズは前半用より0.5cm大きいサイズにしておくのもプロの知恵です。
この「前半は攻め、後半は守り」のシフトチェンジにより、身体の状態に合わせた最適なサポートを受けられます。
後半に足がむくんで痛くなることを見越した、論理的で賢い攻略法と言えるでしょう。
月間走行距離200km以上をこなすためのコスト管理術
ウルトラマラソン完走には、月間200km以上の走り込みが必要と言われます。
しかし、1足2万円前後する最新シューズの寿命は、一般的に600kmから800km程度です。
すべての練習を本番用シューズで行うと、レース当日にはクッションがヘタってしまっている可能性があります。
経済的にも負担が大きくなります。
そこで、練習用と本番用の使い分けが重要です。
普段のジョグや距離踏みには、型落ちのセール品や、耐久性に定評のある高コスパモデル(ワークマンの厚底シューズなども練習には有用)を使用します。
足を作る段階では、あえて重い靴やクッションの少ない靴を使うことで、脚筋力を鍛える効果も期待できます。
そして、週末のロング走やペース走など、質の高い練習の時だけ本番用シューズを履きます。
こうすることで、本番用シューズの鮮度(クッションの反発)を保ちつつ、経済的なランニングライフを継続できます。
本番用シューズの性能を最大限発揮させる慣らし期間

「本番用は新品が良い」と考える方がいますが、これは危険です。
新品のシューズはアッパー素材が硬く、足に馴染んでいません。
また、ミッドソールのクッションも初期状態では硬いことがあります。
いきなり100km走ると、予期せぬ靴擦れを起こすリスクがあります。
レース当日に最高の状態にするためには、「慣らし履き」が必要です。
購入後、最低でも50km、できれば100km程度は走っておきましょう。
何度か洗濯したり、雨の中を走ったりすることで生地が柔らかくなり、自分の足の形にフィットしてきます。
逆に、走行距離が400kmを超えてくると、見た目は綺麗でもクッション性能が低下し始めます。
本番用シューズをおろすタイミングは、レースの1ヶ月から2ヶ月前くらいがベストです。
計画的にシューズを育成し、最高のパートナーとしてレースに連れて行きましょう。
シューズの性能を引き出す高機能ソックスの重要性
シューズ選びと同じくらいこだわってほしいのが「ソックス」です。
普通の綿の靴下では、汗を吸って濡れたままになり、皮膚がふやけてマメの原因になります。
ランニング専用の、吸汗速乾性に優れた高機能ソックスは必須装備です。
特におすすめなのが「五本指ソックス」です。
指が独立しているため、指同士の摩擦によるマメを防ぎ、地面を掴む感覚も鋭くなります。
「Tabio(タビオ)」や「R×L(アールエル)」などの日本製ブランドは、土踏まずを持ち上げるアーチサポート機能も優秀です。
また、雨対策やマメ防止に特化した「Drymax(ドライマックス)」という海外ブランドのソックスもウルトラランナーに人気です。
シューズとソックスの相性もあります。
必ず本番用シューズと本番用ソックスの組み合わせでロング走を行い、問題がないか確認してください。
足首をしっかり固定するヒールロックなど結び方の工夫
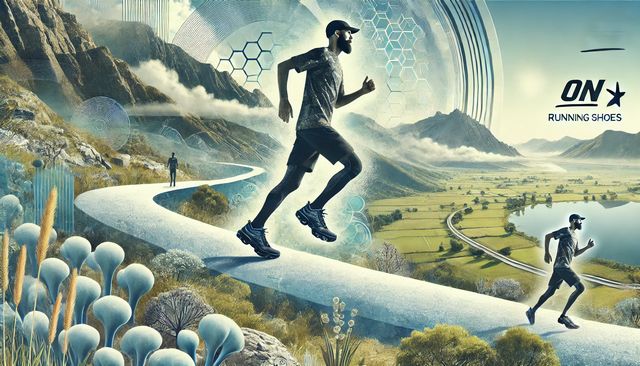
大きめのシューズを履くウルトラマラソンでは、靴紐の結び方一つで快適性が変わります。
特におすすめなのが「ヒールロック(ダブルアイレット)」という結び方です。
シューズの一番上にある、普段使わない予備の穴を活用します。
一番上の穴を使って小さな輪を作り、その輪に対角線の紐を通して締めることで、足首周りを強力にロックします。
これにより、つま先には余裕を持たせつつ、かかとが浮くのを防ぐことができます。
下り坂でも足が前に突っ込まず、爪を痛めません。
靴紐自体も、伸縮性のある紐や、ほどけにくい凸凹加工のある紐に変えるのも有効です。
レース中に紐がほどけると、結び直すために屈む必要があり、疲れた腰に負担がかかりますし、リズムも狂います。
小さな工夫の積み重ねが、100km先のゴールへとつながります。
【まとめ】ウルトラマラソン用シューズについて
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。