インソールずれるという悩みは、靴の中で足が泳いだり、摩擦が増えて痛みにつながったりする厄介な問題です。
靴の中敷きがずれる原因はサイズや素材、汗や汚れなど複合的で、スニーカーの中敷きがずれる状況からビジネス靴まで幅広く起こり得ます。
こうした不快感を避けるには、中敷きがずれない方法を正しく選び、インソール固定方法を使い分けることが近道です。
例えば、インソール固定用の両面テープやインソール固定スプレーは、簡単に導入できる定番の対策です。
スポーツ別に見ると、ランニングシューズやトレランでの長時間走行、横方向の動きが多いバッシュ、通気の良いサンダルなど、シーンにより最適な対策が異なります。
ブランドや製品別の工夫としては、ニューバランスの靴の足型特性や、ドクターショールの製品特性に合わせた合わせ方があります。
手軽さを重視する場合は、100均で入手できるダイソーの固定テープやセリアの固定テープがコストを抑えた現実的な選択肢になります。
本記事では、状況別の手順と注意点を整理し、迷いなく実践できる知識を提供します。
■本記事のポイント
- ずれを招く要因と見極め方
- 靴種や用途別の実践的な固定手順
- 両面テープやスプレーなど固定用品の選び方
- 100均アイテムを含む低コスト対策の使い分け
インソールずれる原因と基本的な対策

歩いているうちにインソールがずれて不快に感じた経験は、多くの人に共通する悩みです。
特にスニーカーや革靴、スポーツシューズでは、わずかな隙間や素材の相性が原因で中敷きが動き、足の安定性を損ねてしまいます。
放置すれば歩行バランスの乱れや靴の変形にもつながるため、原因の特定と適切な対策が重要です。
ここでは、インソールがずれるメカニズムを科学的に解説し、靴の種類や素材に応じた実践的な解決方法を詳しく紹介します。
今日からできる簡単な固定法まで、具体的なステップで解説していきます。
靴の中敷きがずれる原因を正しく理解する

インソールがずれる現象は、単なる靴の「緩み」ではなく、構造的・物理的な要因が複合的に絡み合った結果として起こります。
一般的には、靴内の余剰スペース、素材間の摩擦特性、湿度や温度の変化、貼付け方法の不備などが主因とされています。
特に、歩行時の地面反力や蹴り出し時のせん断力が加わることで、インソールにわずかなズレが生じ、その蓄積が不快な位置ずれとして現れます。
サイズと構造による影響
サイズがわずかに大きい靴では、足と靴の間に「遊び」が生まれ、着地ごとに前後方向の力が生じます。
この力は平均で体重の約1.2倍から1.5倍に達するとされ、その繰り返しがインソールの前滑りを誘発します。
逆に、きつい靴では汗や皮脂により湿度が高まり、摩擦係数が一時的に下がるため、粘着面が緩んで動きやすくなります。
素材間の摩擦特性
靴のライニング(内側素材)とインソール裏面の相性も重要です。
スエード調やナイロン素材のライニングは表面が滑らかで、インソールがEVA(エチレンビニルアセテート)やPU(ポリウレタン)で構成されている場合、動摩擦係数が0.4未満に下がることが報告されています。
この摩擦係数の低下が、歩行中にインソールが少しずつ前後に動く原因になります。
汗や汚れによる摩擦低下
長時間の使用で発生する汗や皮脂、靴下繊維の微粒子は、接触面の摩擦を低下させる潤滑膜として作用します。
特に夏場は靴内の湿度が80%以上に達することがあり、これが粘着性を著しく下げる要因となります。
そのため、インソールが頻繁にずれる人は、湿気対策と清掃の習慣化が不可欠です。
原因の見分け方
● 靴を履かずにインソールのみを押して動くかを確認し、靴内側の摩耗や粉の堆積を点検します。
● つま先側だけが動く場合はサイズや縦方向の遊び、かかと側が浮く場合はヒールカップ形状のミスマッチが疑われます。
● 汗が多い日に特にずれが生じる場合は、吸湿性や通気性の不足が関与していると考えられます。
これらを踏まえ、インソールずれを単なる「靴の不良」と捉えず、素材特性・環境条件・使用頻度を含めた多面的な分析を行うことが、正確な対策の第一歩です。
スニーカーの中敷きがずれる場合のチェックポイント

スニーカーの中敷きがずれる場合、日常使用での着脱頻度やシューレースの締め具合が直接影響します。
特に、踵のホールドが不十分な場合、足が前方に滑りやすくなり、結果的にインソールが押し出される形でずれていきます。
これはウォーキングや通勤など、軽度の繰り返し動作でも発生します。
サイズとフィット感の見直し
まず確認すべきは、足長・足囲・甲の高さの適合性です。
日本靴医学会の基準では、足と靴の長さに5から10mmの余裕が理想とされていますが、これを超えるとインソールが動く余地が生まれます。
また、足幅が広い人が細身のスニーカーを履くと、インソールが歪み、片側だけが浮きやすくなります。
シューレースの締め方とヒールロック
スニーカーでは「ヒールロック」と呼ばれる結び方が有効です。
最後の穴にシューレースを通し、輪を作ってクロスさせることで、踵のフィット感を高めることができます。
これにより前滑りが軽減され、インソールのずれも抑制されます。
インソールの取り外し構造
取り外し式のインソールは便利な反面、固定が甘くなりやすい構造です。
使用後は毎回取り出して乾燥させ、裏面の埃や繊維をブラシや乾いた布で落としましょう。
縫い付け式の場合は、経年で接着面が弱くなるため、修理専門店での再接着も検討できます。
素材と表面状態の管理
ライニング素材が滑るタイプ(ナイロン、ポリエステル系)では、インソールの裏面を少し粗く加工することで摩擦を増やせます。
サンドペーパーの目安は400番程度で、軽く擦るだけで十分です。
これは靴メーカーのメンテナンス推奨法としても紹介されています(出典:日本皮革産業連合会「靴のケアとメンテナンス」)。
このように、スニーカーの中敷きがずれる場合は、単に粘着剤を追加するのではなく、構造的なフィットと摩擦特性の最適化から取り組むことが長期的な解決につながります。
中敷きがずれない方法を実践する基本ステップ

インソールのずれを防ぐには、段階的なアプローチが最も効果的です。
対症療法的にテープを貼るだけでは根本解決には至らず、環境整備・清掃・素材の組み合わせまで考慮する必要があります。
ステップ1:清掃と乾燥
まず行うべきは、靴内部とインソール裏面の徹底清掃です。
特に微細な粉塵や皮脂膜は摩擦低下の主要因となるため、アルコール系ウェットシートで拭き上げ、完全乾燥させます。
乾燥時間は室温で約1時間が目安です。
ステップ2:素材相性の確認
次に、靴内の素材とインソール裏面の組み合わせを確認します。
ナイロン×EVAの組み合わせは滑りやすく、キャンバス×PUは比較的安定しています。
相性が悪い場合は、滑り止めシート(シリコンまたはメッシュタイプ)を薄く敷くと効果的です。
ステップ3:可逆的な固定法を選ぶ
いきなり接着剤で固定すると、交換や調整が難しくなります。
最初は両面テープや仮固定シートを使用し、数日使って安定性を確認しましょう。
これにより、靴やインソールを傷めずに問題箇所を特定できます。
ステップ4:サイズ調整で遊びをなくす
靴の中に余白が多い場合は、ヒールグリップや前滑り防止クッションを併用します。
これにより、足と靴の一体感が高まり、インソールへの横ずれ圧力が軽減されます。
ステップ5:使用後のメンテナンス
インソールを定期的に取り出して乾燥・清掃することで、粘着や摩擦が安定します。
週に一度程度のメンテナンスを習慣化することが、最も確実なずれ防止策です。
これらの工程を一度確立しておくことで、どんな靴でも安定した履き心地を維持できるようになります。
インソール固定方法の種類と選び方

インソールを安定させるための固定方法には、主に「両面テープ」「固定スプレー」「固定シート」「接着ゲル」の4種類があります。
それぞれに特徴があり、使用する靴の種類・環境・目的によって最適解が異なります。
単に「粘着力が強いものを選べば良い」というわけではなく、靴素材への影響や剥がしやすさ、再利用性などのバランスを考慮することが重要です。
固定方法ごとの特徴と選定基準
固定力を優先するか、メンテナンス性を重視するかによって選ぶべき方法が変わります。
以下の表に、代表的な固定手段の比較をまとめます。
| 固定方法 | 固定力 | 剥がしやすさ | 靴素材への影響 | コスト | 再利用性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両面テープ | 高い | 中 | 糊残りの可能性 | 低 | 低 |
| 固定スプレー | 中から高 | 中 | 揮発後は安定 | 中 | 中 |
| 固定シート | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 |
| 接着ゲル | 中 | 高 | 低 | 中 | 中 |
このように、固定力だけを基準にすると失敗することがあります。
例えば、両面テープは強力ですが、革靴や合皮素材に糊残りを起こすことがあり、靴内部を傷める可能性があります。
一方で固定シートやゲルは、摩擦で保持するタイプのため、繰り返し使用できる点で環境負荷が低い選択肢とも言えます。
スポーツ用途(ランニングシューズ・バッシュなど)では、高い固定力と柔軟性を両立できる固定スプレーや接着ゲルが適しています。
ビジネスシューズや日常用スニーカーでは、剥がしやすさとメンテナンス性を優先した固定シートが理想です。
インソール固定用の両面テープを使うメリット

両面テープは、もっとも手軽に導入できる固定手段です。
粘着力が安定しており、低コストで導入できるため、多くの靴メーカーも一時固定や工場出荷時に使用しています。
手軽で確実な施工性
貼付けは単純で、必要な形にカットして貼るだけです。
位置合わせの際は、まず剥離紙を半分だけ剥がして仮止めし、位置が決まってから残りを剥がすとズレを防げます。
この作業で得られる精度は非常に高く、接着面積が小さい場合でも十分な安定性が得られます。
季節や環境による影響
両面テープの粘着剤は、温度によって性能が変化します。
気温が10℃以下になると粘着力が立ち上がりにくくなるため、貼付け前に室温に慣らすか、靴内部をドライヤーで軽く温めてから作業すると安定します。
また、湿度の高い季節には、貼付け前に靴内を乾拭きして水分を完全に除去しておくことが大切です。
メンテナンスと取り外しのポイント
剥がす際は、角からゆっくりと持ち上げ、糊残りが出た場合はアルコール系のクリーナーで優しく除去します。
強く擦るとライニングを傷つける恐れがあるため、専用の粘着クリーナーを使うのが安全です。
最近では、靴素材を傷めにくい低残渣タイプのテープも登場しています(例:3M製再剥離型アクリルテープなど)。
メリットと注意点のまとめ
●コストが安く、試しやすい
●施工が簡単で、即日効果を得られる
●糊残りや素材劣化には注意が必要
●高温多湿の環境では定期交換が望ましい
短期的な使用や、頻繁にインソールを交換する人に最適な方法といえます。
インソール固定スプレーの特徴と使い方

固定スプレーは、広い面積に均一に粘着性を付与できるため、部分的な浮きを防ぎながら自然なフィット感を維持できる点が特徴です。
主に靴メーカーやリペア業者でも使用されており、両面テープよりもムラの少ない仕上がりが期待できます。
固定スプレーの原理と効果
固定スプレーには「感圧型粘着剤」が使われており、表面に薄い膜を形成して摩擦係数を高めます。
この膜は揮発後も残留してインソールを固定しつつ、再剥離が可能な構造を保ちます。
特にEVAやPU素材の裏面に適しており、繰り返し貼り直しても粘着力が大きく低下しません。
使用手順
1 換気を確保した場所で使用する。
2 靴内側とインソール裏の両面に10から15cmの距離から均一に噴霧する。
3 30秒程度放置し、半乾きの状態で圧着する。
4 数分間静置して粘着が安定するのを待つ。
この工程により、糊残りを抑えながら密着度を確保できます。
においが気になる場合は、完全乾燥後に着用するのが望ましいです。
注意点と安全性
固定スプレーには有機溶剤が含まれるため、皮膚が敏感な人や密閉空間での使用は避けるべきです。
各メーカーでは「使用前のパッチテスト」を推奨しており(出典:厚生労働省 化学物質情報)、初回は少量で試すのが安全です。
メリットの整理
●広範囲の密着に適しており、凹凸面でも安定する
●再剥離が容易で、靴を傷めにくい
●揮発後に粘着が安定するため、長時間使用に向く
●使用環境(温度・湿度)による性能変動が少ない
固定スプレーは、日常使いからスポーツシューズまで幅広く活用できる万能型の固定方法です。
ダイソーの固定テープを使った手軽な対策

ダイソーの固定テープは、手軽に入手できるうえにコストパフォーマンスが高い点で人気があります。
強力な粘着力を持つタイプから、再剥離可能なタイプまでラインナップが豊富で、試行錯誤に向いています。
使用時の工夫と貼り方
テープを靴のつま先部分に短冊状にカットし、放射状に貼るとより強力な固定力を得られます。
この貼り方は歩行時の屈曲に対して剥がれにくく、力の分散にも優れています。
靴の材質によっては、踵側を中心に貼るよりも土踏まず方向へ配置したほうが安定する場合もあります。
粘着力の維持と温度管理
テープの粘着力は、温度と湿度に大きく影響されます。
貼付け前にはアルコールで靴内部を清掃し、完全に乾燥させることで粘着性能を最大化できます。
特に夏場は汗や湿気で剥がれやすくなるため、貼り替えの頻度を週1から2回に設定するのが理想です。
メリットと使用上のポイント
●低コストで試しやすく、失敗しても再調整可能
●汎用性が高く、ほとんどの靴素材に対応
●季節ごとにテープの厚みを変えることで最適化できる
靴を頻繁に履き替える人、あるいは短期間で効果を確認したい人には、最初に試すべき方法と言えます。
セリアの固定テープで試すコスパ対策

セリアの固定テープは、ダイソー製よりもやや薄手で、段差を作らず自然に装着できるのが特徴です。
靴の見た目を損なわず、軽度のずれ対策に適しています。
貼り方と位置の工夫
踵側と土踏まず側に分けて貼ると、歩行時のねじれや回転方向のズレを防ぎやすくなります。
特に女性のパンプスやスリッポンなど、固定面が少ない靴に有効です。
長期使用のコツ
テープの粘着面は、時間とともに埃を吸着して粘着力が落ちます。
そのため、週単位で剥がして清掃・貼り直しを行うことで性能を維持できます。
剥がした後はアルコールで靴内部を軽く拭き、乾かしてから新しいテープを貼るのが理想的です。
メリットと留意点
●目立たず自然な仕上がりで美観を損なわない
●薄手で段差ができにくく履き心地が良い
●定期的なメンテナンスが必要
セリアの固定テープは、軽度のずれや見た目を重視する人に適したコスパの良い選択肢です。
インソールずれるトラブル別の具体的な対策
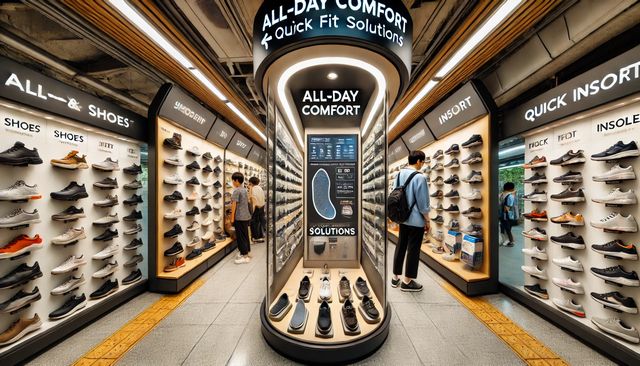
インソールのずれは、靴の種類や使用環境によって原因も対処法も大きく異なります。
たとえば、激しい動きが求められるバッシュでは衝撃とせん断力が問題となり、サンダルでは固定点の少なさがずれを誘発します。
一方で、ランニングシューズやトレランシューズでは、長時間の使用や汗による摩擦低下が影響します。
さらに、ブランドや素材特性によっても安定性の差が生じます。
ここでは、用途別にインソールずれの発生要因を掘り下げ、それぞれに最適な固定・改善策を詳しく解説します。
バッシュでインソールがずれる時の対処法
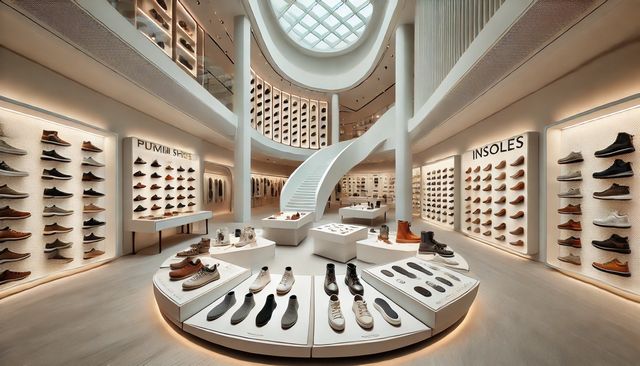
切り返しやジャンプ着地で生じる急峻なせん断力と衝撃は、インソールの前後・左右方向の移動を誘発します。
バスケットボールの着地局面では、垂直方向の床反力が体重の数倍に達することがあると報告されており、微小な遊びや粘着低下があるだけで位置ずれが連続的に積み重なります(出典:米国国立衛生研究所PubMed Central収載の着地研究論文)。
このため、摩擦確保と足部固定、そして貼付面コンディションの三点を同時に整えることが要になります。
まず、足甲から踵にかけての固定を高めるため、最後のハトメを活用したヒールロックを採用します。
ヒールロックは踵骨周囲の浮きを抑え、前方への足滑走を減らすことで、インソール表面に加わる前後せん断を低減します。
インナースリーブやワンピースタンを備えたモデルでは、甲部のテンションを段階的に上げると、足背の圧迫を過度に高めずにフィットを確保できます。
加えて、シューズ内部のライニングがナイロンやマイクロファイバー系で平滑な場合、インソール裏面の清掃と乾燥に加え、薄手のメッシュ状固定シートで面摩擦を底上げすると、動摩擦係数が上がり横方向のずれを抑えやすくなります。
貼付材の運用では、つま先側は広め、土踏まず側は狭めにテープ面積を配分します。
前足部は屈曲が大きく剥離が起こりやすいため、短冊状にカットして放射状に配置すると屈曲追従性が上がり、シワや端浮きを抑制できます。
練習前には必ず貼付面の脱脂を行い、アルコール拭き後に完全乾燥させてから施工します。
温度が低い環境では粘着力の立ち上がりが遅れるため、シューズ内を短時間ドライヤーで温めるなどの前処理が安定化に有効です。
週単位での点検と貼り替えをルーティン化し、糊残りが見られた場合は専用クリーナーで除去してライニングを保全します。
サンダルでずれを防ぐためのポイント

サンダルは開口部が大きく、足と接触する固定点が限られる構造のため、インソール面でのグリップ確保とストラップの力学的配置が安定性を左右します。
特に水辺や高湿環境では、足底とフットベッドの間に薄い水膜が形成され、実効摩擦が低下しやすくなります。
まずは面ファスナーやバックルの調整幅を最大限に活用し、甲側と踵側のストラップテンションを独立して最適化します。
甲側で前方滑走を抑え、踵側で後方浮きを止めると、足部の回転モーメントが小さくなり、フットベッド上のせん断力が減少します。
フットベッドがEVAやTPUでやや滑りやすい場合は、薄手の固定シート(メッシュやマイクロスエード調)を敷いて表面摩擦を補い、必要に応じて微量の固定スプレーで面全体の密着を均一化します。
水濡れが想定される場面では、両面テープは粘着層の水分吸収で性能低下や糊残りが起こりやすいため、ゲル系の再剥離シートのほうが実用的です。
ゲルは粘着ではなく凝着・粘弾性で追従するため、乾湿変化に対して比較的安定し、足裏感触もマイルドに保てます。
ストラップの当たりが強くなると循環や皮膚への負担に直結するため、テンションは運動前後で微調整します。
特に炎天下では足部体積が一時的に増えるため、出発時の適正締め付けが時間経過とともに過緩・過緊張に偏らないよう、休憩時に再調整する習慣をつけると安定性と快適性を両立できます。
合わせて、使用後はフットベッドとシートを水拭きして砂粒を除去し、完全乾燥させることで、次回使用時の摩擦低下を予防できます。
ランニングシューズで起こるずれの原因と解決法

長距離走では、汗量増加と足部体積の一時的な増大(運動性浮腫)が進み、レース後半に前滑りが起きやすくなります。
また、トゥスプリング(つま先反り)やヒールカップの形状が足型と一致しないと、蹴り出し時に前足部へ偏ったせん断力が発生し、インソールの前方移動を助長します。
サイズ選定では、夕方の足で試着し、足長に対して約5から10mmの余裕を目安にしつつ、ワイズと甲高の適合を重視します。
余裕が大きすぎると遊びが増え、逆にタイトすぎると汗で摩擦低下が顕著になり、どちらもずれを助長します。
シューレースは足背圧を過度に高めない範囲で段階的にテンションを上げ、最後のアイレットを使うヒールロックを導入すると踵のホールドが向上します。
これにより、接地から離地までの間に生じる前方への足滑走が抑制され、インソール表面に作用する前後せん断が低減します。
ミッドソールが高反発のモデルでは、着地後の復元局面で足部が僅かに前方へ押される印象が出ることがあるため、ヒールカップ形状の相性確認と、足型に合うインソールアーチ高の再調整が有効です。
固定剤の使い方は、レース本番での不確実性を避けるため計画的に行います。
固定スプレーは広範囲に極薄で均一塗布し、前日施工で完全乾燥させると、当日の湿度変化に影響されにくく、面全体の粘着が安定します。
両面テープを併用する場合は、つま先側の短冊配置で屈曲追従性を確保し、踵側はU字に小面積で補助的に貼ると剥離しにくくなります。
インソール素材が吸湿しにくいEVAベースの場合は、吸汗速乾ソックスで足裏の水分を管理し、インソール表面の潤滑化を抑えると、摩擦バランスが整いずれの再発が減ります。
走行距離が伸びる時期は、週ごとに貼付面の清掃と貼り替えを行い、接着界面の劣化を予防すると安定性が持続します。
トレラン用シューズでのずれ対策と工夫

トレイルランニングでは、舗装路とは異なり不整地での前後・左右・回旋方向の力が連続的に発生するため、インソールのずれが起こりやすい環境が整っています。
特に下り坂では体重の2倍を超える荷重が前足部に集中し、つま先方向への滑りが顕著に現れます。
これを抑えるには、靴のサイズ・内部容積・固定方法の三点を精密に調整する必要があります。
サイズ選定とトゥボックスの見直し
トレイルシューズは「つま先の余裕」を設ける設計が多いですが、これが過剰だと下りで足が前方に移動し、爪先に衝撃とインソールのずれが同時に発生します。
ハーフサイズ下げる、またはトゥボックス形状を細めにすることで、足の前滑りを抑えられます。
トゥガードの柔軟性が高いモデルを選ぶと、圧迫感を避けつつ安定性を得ることが可能です。
汚れ・異物の侵入防止
泥や砂が靴内に侵入すると、インソールとライニングの間に微細な粒子が入り込み、摩擦を著しく低下させます。
これを防ぐためには、ゲイターの装着が推奨されます。
ゲイターは砂防止カバーで、足首部を覆うことで靴内への異物混入を防ぎ、摩擦低下を防ぐ補助的役割を果たします。
使用後は必ず靴内部を乾燥させ、ブラシで砂塵を落としてから再度インソールをセットします。
固定テープの最適配置
トレラン用の靴は屈曲・ねじれが激しいため、直線的にテープを貼ると剥離や応力集中を起こしやすくなります。
つま先から踵にかけてS字状に固定テープを配置すると、荷重方向に追従しやすく、屈曲時のテンション分散に優れます。
さらに、テープを2から3本に分割して貼ることで剥離しにくくなり、メンテナンス時にも再施工が容易です。
湿度・温度条件への対応
山岳環境では気温差が大きく、湿度の変化によって粘着力が左右されることがあります。
低温下では固定剤の硬化が遅れ、高温下では軟化して粘着層が弱まるため、登山・トレイル前日に室温で施工し、現地では粘着剤の再活性化を防ぐために完全乾燥させた状態で使用するのが理想です。
ニューバランスの靴でずれを防ぐおすすめ方法

ニューバランスは、複数の木型(ラスト)を用意することで、足の形状やワイズに合わせた精密なフィットを提供しているブランドです。
適正サイズとワイズを誤ると、インソールが靴内で遊び、ずれや歪みが発生しやすくなります。
そのため、まずは「D(標準)」「2E(広め)」「4E(特広)」といったワイズ表記を確認し、自分の足囲に合ったモデルを選ぶことが重要です。
フィット感を重視したサイズ選定
特に踵周りのフィットが甘いと、足がわずかに前方へ動き、インソールに摩擦ストレスが集中します。
ニューバランスの「SL-1」「SL-2」などのラストは踵を包み込む設計で、これらのモデルを選ぶとホールド感が高まります。
また、アッパー素材が柔らかすぎると横方向のずれが生じやすくなるため、サポート性の高いメッシュやTPU補強のあるモデルが望ましいです。
インソール裏面の処理と清掃
ニューバランスの取り外し式インソールは裏面に微細な凹凸パターンが施されているものもあります。
これは滑り止め効果を高めるためで、滑らかな裏面タイプよりも安定します。
もしフラットな裏面のモデルを使用している場合は、薄手の滑り止め固定シートを敷き、摩擦を補強します。
清掃は週に一度を目安に行い、湿気を含んだまま使用し続けると粘着層の劣化を早めるため、陰干しで完全乾燥させてから再装着します。
再貼付けのタイミング
インソールが浮き始めたり、音鳴り(キュッという摩擦音)が出る場合は、固定力低下のサインです。
粘着剤やシートをそのまま再利用するのではなく、一度剥がして貼付面を清掃し、新しい固定材に交換することで安定性を維持できます。
このように、ニューバランスの靴は構造的な精度が高いため、適切なメンテナンスを行えば、インソールのずれを長期的に防止できます。
ドクターショール製インソールの安定感を高める工夫

ドクターショールのインソールは、医療知見に基づいた設計が特徴で、ジェル素材・EVAフォーム・衝撃吸収パッドなど、製品ごとに構造が異なります。
ジェルタイプは高いクッション性を持つ反面、表面が滑らかなため、靴内部の素材との摩擦相性によっては動きやすくなる場合があります。
素材の相性と安定化対策
靴内が合成皮革やナイロンライニングの場合、ジェル表面との摩擦係数が低下しやすく、動摩擦係数が0.3から0.4程度まで下がることがあります。
このような組み合わせでは、裏面に薄いメッシュ状固定シートを敷くことで摩擦を補い、ずれを防止します。
メッシュの目が粗いほどグリップが強まる傾向にありますが、厚みが増すと容積が減るため、窮屈感がないかを必ず確認します。
フィットと快適性のバランス
ジェル素材の柔軟性は足裏への圧力を分散させますが、過度に柔らかい素材は「踏み込み時の遅れ」を感じやすく、靴内での位置変化につながることもあります。
用途別に硬度の異なるモデルを選ぶことで、安定性と衝撃吸収の両立が図れます。
たとえば、立ち仕事用のモデルは長時間安定性を優先しており、ランニング向けモデルは動的変形を考慮して硬度が高めに設定されています。
安全性と使用上の注意
皮膚が敏感な方やアレルギー体質の方は、メーカー公式サイトでも推奨されているように、長時間使用前に短時間試用を行い、異常がないことを確認します(出典:ドクターショール公式サイト)。
また、洗浄の際は中性洗剤を使用し、陰干しで完全乾燥させてから再装着することで、粘着や素材劣化を防げます。
ドクターショールのインソールは正しいメンテナンスを行うことで、快適性を維持しながら長期間の安定を実現できます。
【まとめ】インソールずれるについて
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


